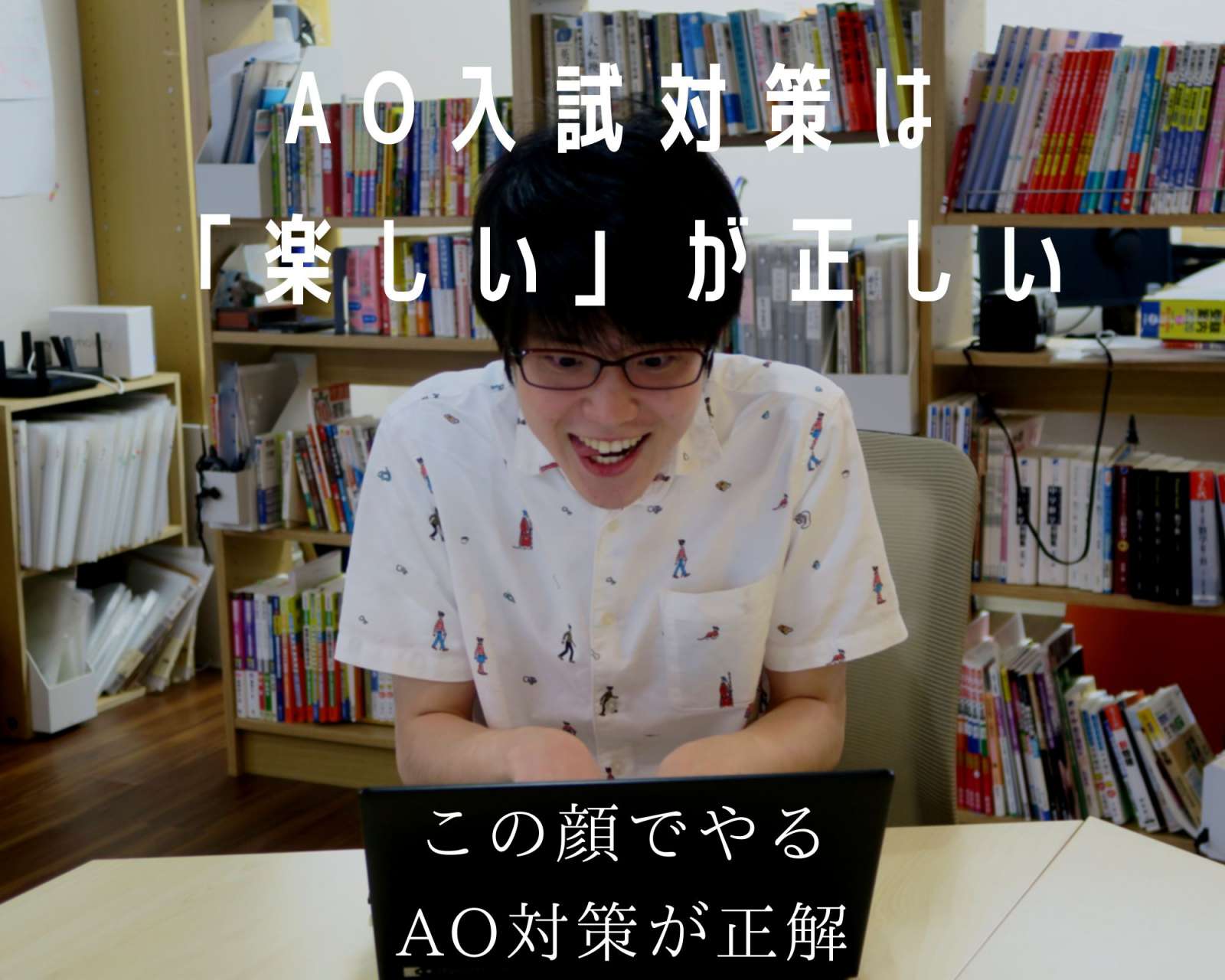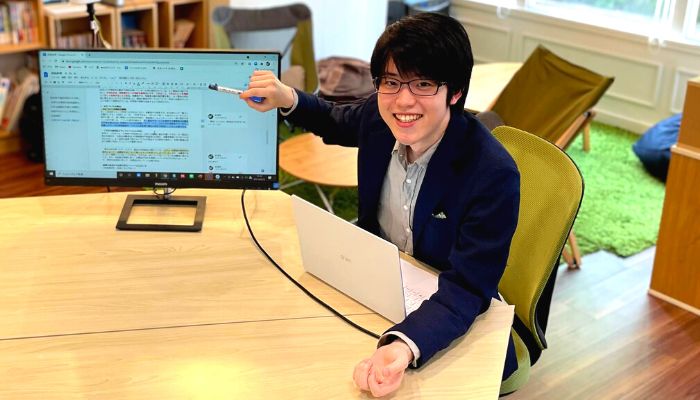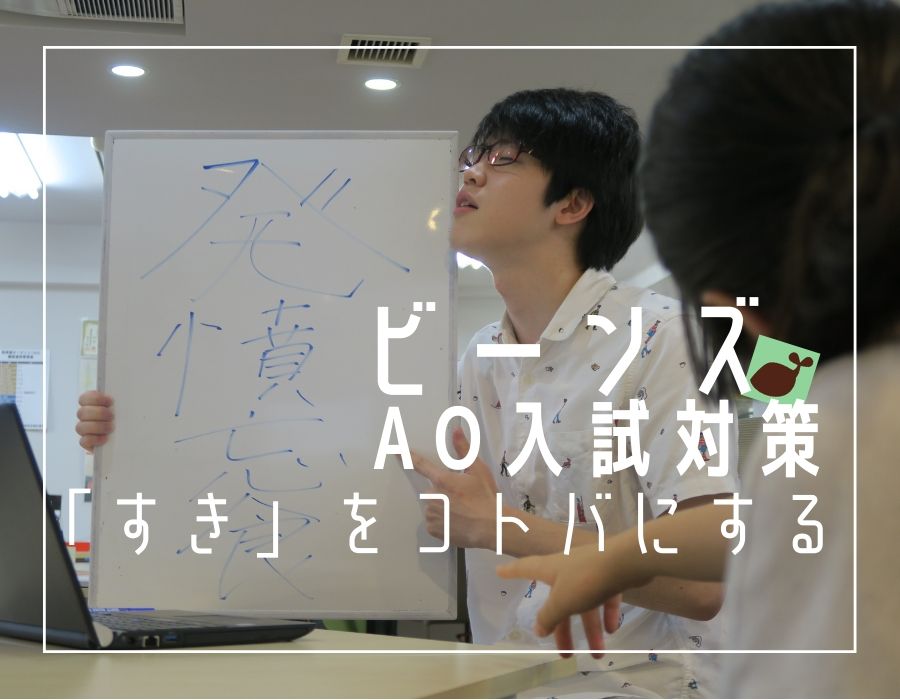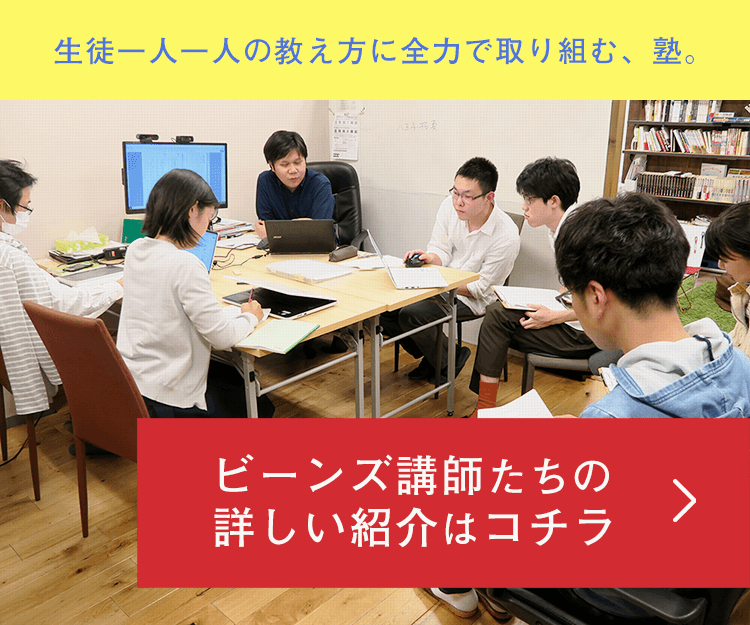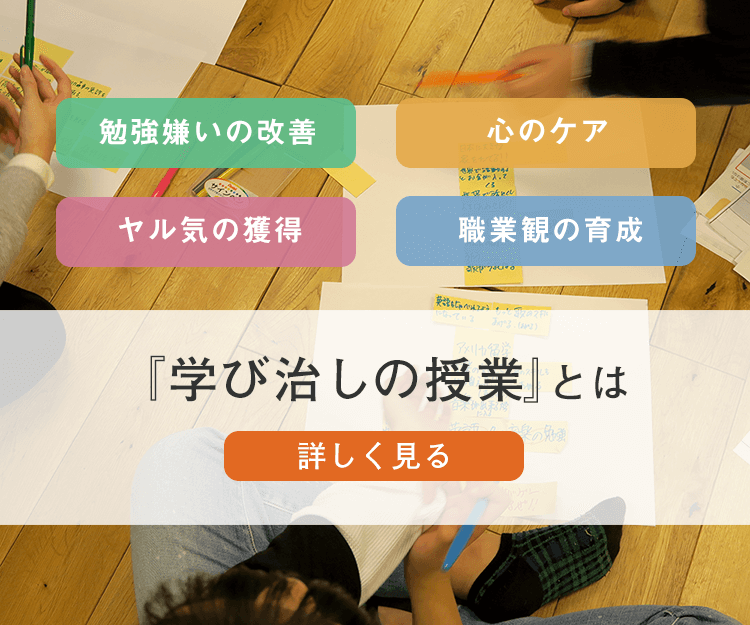不登校・勉強嫌いもAO入試/推薦入試は目指せる①
「保護者さまの心構えについて」
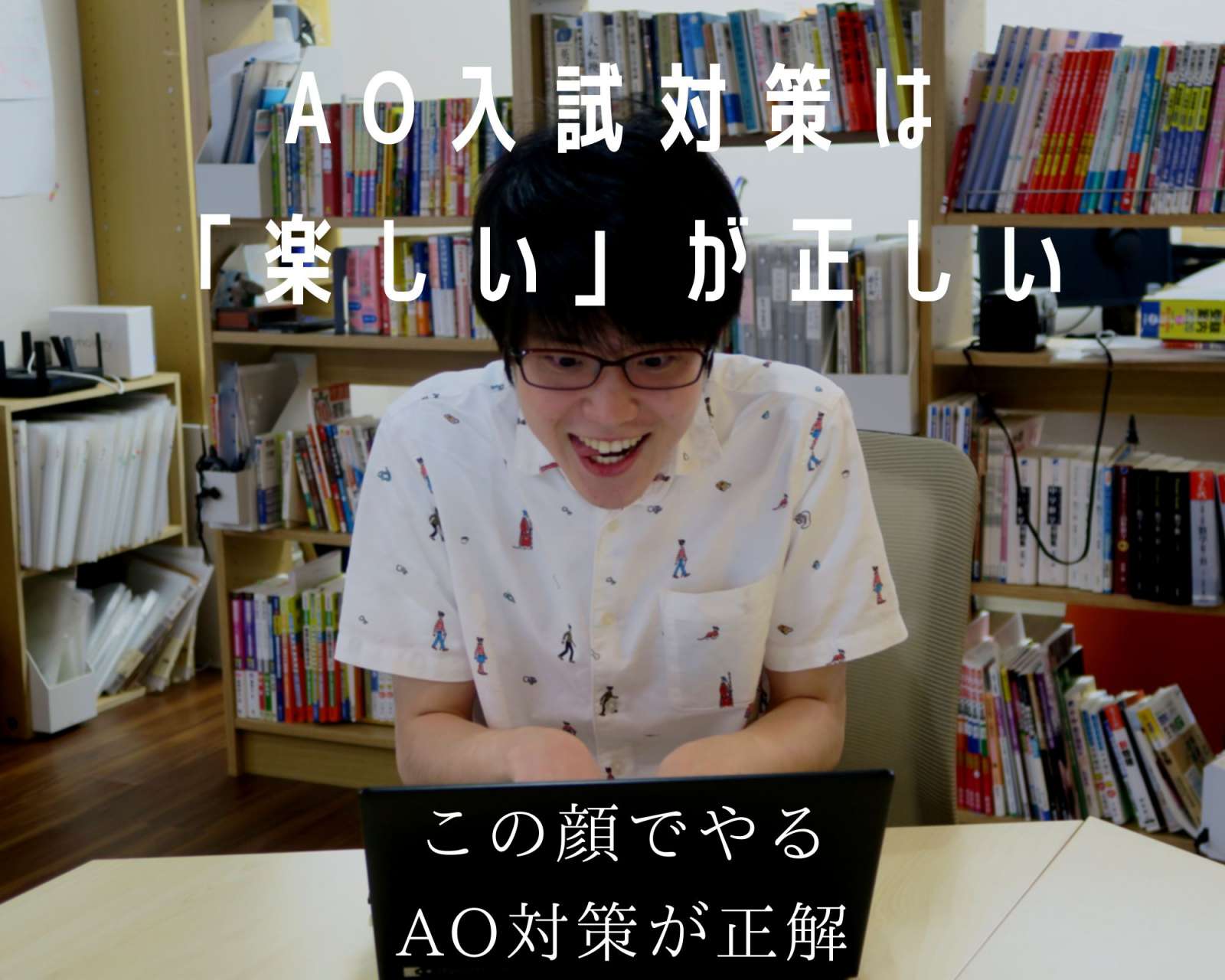
今回の記事では、総合型選抜(旧AO入試)の概要、お子さまが総合選抜を目指す際の保護者さまの心構え、ご家庭でお願いしたいフォローについて、お伝えします。
(本記事では「総合型選抜」を旧来の「AO入試」と呼称します)
特に「(科目)勉強は嫌いだけど、好きなことはバッチリある」お子さまと、その保護者さまに読んでいただきたいです。
ビーンズのAO入試/推薦入試対策のリーダーとして活躍し、自身も講師として合格者を輩出し続ける学習支援塾ビーンズ塾長の長澤がお送りします。
長澤啓(Nagasawa kei)
学年ビリから二浪し東京大学へ入学。ビーンズの活動が楽しすぎ、留年。経済学部経営学科卒。
ビーンズが積み上げてきたノウハウを「ビーンズメソッド」として文字化し、より洗練するのがメインのお仕事。さらに、親との衝突が絶えなかった自身の経験を活かし、保護者とのコミュニケーションにも注力。保護者さまと月100件以上やりとりをしながら、ビーンズ流の保護者さまサポートを拡充中。最近は副代表として、講師の採用育成プランの策定・外部協力者との渉外・経営企画までマルチにこなす。趣味はビールを飲みながら出汁巻き卵をつくること。
■インタビュー/詳しい自己紹介
学校の勉強についていけなかった僕が東大に合格するまでと親と対立した日々について
もくじ
不登校・勉強嫌いもAO入試/推薦入試は目指せる①「保護者さまの心構えについて」
AO入試(推薦入試全般も含めます)を目指しているお子さまがいる保護者さまにやってほしいこと……
まず最初にやっていただきたいのは、お子さまに先駆けて「AO入試」や「推薦入試」の最新情報を調べていただくことです。
たとえば、以下のような情報です。
・拡がるAO入試枠
東洋経済新聞ONLINE 「青田買い」「AO入試」が今後も増え続ける必然 「学力だけ」では大学に入れなくなりつつある
・東京大学も始めたAO入試 (以下、東京大学のリンクへ飛びます)
※東京大学高大接続研究開発センター「キミの東大」より 「大推薦生インタビュー・全10学部まとめ―特集:よくわかる東大推薦入試(3)」
・早慶のAO入試の動向
※「早稲田大学の推薦入学は4割 学力重視型入試:推薦(AO含む)=6:4の比率」
(参考:WASEDA ONLINE キャンパスナウ 2016 早春号 早稲田大学の入試改革について鎌田薫総長が記者説明会で想いを語る)
AO入試が生まれた背景って?
元々、ペーパーテスト入試(=大学の一般入試)は大量の受験者から効率的に合格者を選抜するための仕組みでした。
しかし、ペーパーテストの点数だけでの選抜だと、
受験生が大学に入る目的を確認できない。受験生が大学でやりたいことを考える機会が入学までない。
そして、そのまま主体的な学びをせずに大学を卒業する学生が存在してしまうという課題がありました。
そこで、ペーパーテストでは測れない「志願者の価値・入学の熱意・入学後の可能性」を評価することを目的としてAO入試がうまれます。
日本初のAO入試は、慶応大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で1990年に実施されました。
AO入試が広まるにつれ、AO入試に対するネガティブな評価も増えました。
例えば「受験生の数合わせとしてAO入試が使われているのでは」等の意見です。
しかし「志願者の価値・入学の熱意・入学後の可能性」を測りたい大学側のニーズの高まりから、今もなおAO入試は広まり続けています。
ここまで「AO入試が生まれた背景」についてお伝えしました。
要は「ペーパーテストのみの選抜に限界を感じた大学側が、AO入試を順次取り入れつつあり、その募集人数も増え続けている」というわけです。
ペーパーテスト=一般入試は
「親と学校に薦められるまま受験した」とか
「みんなが大学に入っているから」といった理由でも点数をとれれば合格できます。
一方で、AO入試(そして推薦入試)では「そもそも自分は大学で何を学びたいのか」がはっきりして、自分で表現できなければ合格できません。
当然、AO入試(推薦入試)の受験生たちは、自分自身と向き合い、自己分析を行った時間が長く、大学で何がしたいのかをはっきりさせている可能性が高いのです。
大学側も「自己分析をしっかりしている学生のほうが、大学入学後の学びを主体的に行う」と期待しています。
実際にそれを裏付けるデータも出てきているので、それゆえ今後もAO入試/推薦入試は大学入試形態の中心になっていく流れは変わらないと思います。
加速するAO入試/推薦入試の多様化!「大学ごとに異なる入試形態」
現在「AO入試/推薦入試の多様化」が加速しています。
一言で「AO入試/推薦入試」といっても入試内容は多種多様です。
以下は、一例です。
▼AO入試/推薦入試で課される課題(一般的なケース)
【事前に課されるもの】
・エントリーシート(自己推薦書・志望理由書)
・高校までの自分の活動をまとめた資料(活動報告書)
・高等学校における成績
・簡単な学力検査
【試験当日に課されるもの】
・講義を受けてのレポート作成
・集団討論
・小論文
・面接
かつては、推薦入試とは違い、高校の評定や学力などを評価していなかったAO入試ですが、高校の評定や「学力の基準」(英語力の検査)などを設ける大学も増えているので注意が必要です。
例えば、英検などの検定試験のスコアを出願資格として求める大学もあります。
また、AO入試/推薦入試では、その大学への「専願」を出願条件にしている場合もあります。
一般的なAO入試/推薦入試の典型例を以下にあげてみましょう。
一次選考
《事前提出》
・エントリーシート(自己推薦書・志望理由書)
・活動報告書(スライド資料など)
・高等学校における成績
本選考
・面接
・小論文
ここまでで保護者さまにご理解いただきたいのは、AO入試/推薦入試の概要と、各大学でAO入試/推薦入試の入試内容は違うということです。
試験はまだ先であっても、保護者さまが先んじて各大学の入試概要に目を通しておくと不安がなくなりますのでお勧めです。
ご家庭でできるAO入試/推薦入試の準備「日々の家庭の会話から」
子どもの「好き」をストーリーにしていく
AO入試の情報収集が終わったら、次に保護者さまにやってほしいことは、「キラーストーリー」(面接官に「この生徒を入学させたい」と思わせるストーリー)の芽をお子さまから引き出すことです。
そのためには、ご家庭で以下のことを意識してみてください。
・ご家庭の会話の中で「子どもが好きなことを話し始めたら」深掘りしていく
・「<>子どもが好きなこと」と大学で学ぶ学問分野が繋がらないか探してみる
特に、お子さまの好きなことが、大学での学びにつながる可能性があることを意識させてあげてください。
ここでポイントは、大学の学問分野とひもづけづらいものがお子さまの好きなものである場合です。
お子さまの好きなものが日本史の場合は、学問分野とのつながりが、お子さまに自身にも分かりやすいです。
お子さまが仮に昆虫好きの場合、一見すると学問分野とのつながりが分かりにくいでしょう。
そういう場合にも、丁寧に大学の研究分野を調べていけば大学の学部(応用昆虫学の学べる農学部や理学部、生命環境学部……)につながります。
子どもは自分の好きなものが学問分野につながると夢にも思っていない場合があります。ここで大人の手助けがいるのです。
「あなたの好きなことって、〇〇大学でこんな研究があるみたいよ」と伝え、お子さまの好きなことが大学の学問分野に繋がっていることをお子さまに意識させることがポイントです。
| ※とはいえ、相手は何かとデリケートな思春期のお子さまです。 「自分で調べるからお母さん・お父さんは黙ってて!」と言われた場合は、黙ってその場から立ち去り、対応は私たちのようなプロにお任せしましょう。 「子どもから反応がなくてもOK」くらいの期待値で話しかけることが重要です。 |
「裏打ち力」を身につける方法は、情報収集と語彙力、そして楽しさ!
例えば、AO入試/推薦入試へ向け「地方のインバウンド観光増加策」という題で、発表資料をつくるとします。
この時大事になるのが、「裏打ち力」です。
「裏打ち力」とは、自分が伝えたい意見の基礎となる先行事例を見つけ、自身の意見を固めることです。
自分の意見を補強する先行事例を資料に豊富に織り込むことで、大学側へ本気度が強く伝わります。
この「裏打ち力」をつけるためには「子ども自身が好きなことについて詳しい情報を引き出してくる方法」を伝えることが重要です。
ご家庭でお子さんの「裏打ち力」をつけるには、ふたつのポイントがあります。
ひとつめが情報収集の方法
ふたつめが語彙力
です。
情報収集の方法
ひとつめの情報収集方法についてです。
毎年のことですが、AO入試のエントリーシートや発表資料をつくるにあたって「情報まとめサイト」やQ&Aサイト、SNSを情報の収集源にしている生徒が多いです。
入塾当初「〇〇(AO入試で話したいこと)について調べてる?」という質問に対し、「はい!」って答えてくる生徒のほぼすべてがウィキペディアか、まとめサイト、TwitterなどのSNSからの情報を話します。
省庁のサイト、統計データ、各白書はもちろん、新聞も読んでいない状態です。
もちろんSNSで情報収集することはよいのですが、それのみで先行事例を調べたとか、発表資料の情報源にしてはいけませんね。
「ええっ!」っと思った保護者さまもいらっしゃっると思いますが、驚いてはダメです。
高校生が省庁のサイトや統計データ、白書というものの存在を知らないのは当たり前と思いましょう。
新聞だって彼らからすると遠い存在です。ここは大人が「SNSであたりをつけたら、省庁のサイトや白書も見てみよう」と優しく声掛けし、信用度の高い情報源にアクセスすることを伝えます。
語彙力
ふたつめの語彙力についてです。
本章のエッセンスを1分でまとめました!
省庁のサイトや統計データ、白書を読んだとしても、受験生は内容を理解できないことも多いと思います。
なぜなら高校生の多くは、「グローバル化」「人権」「弾圧」「抽象的」「相対的」といった言葉をイメージできていないからです。
例えば、「グローバル化」という言葉を聞いた場合、大人は言葉の裏にある様々なイメージを思い浮かべます。
※イメージとは、言葉にひもづく「絵」や風景のことです。
目の前にあるiPhoneを見たときに、大人であれば様々なイメージが浮かんでくると思います。
ある人は、「これもグローバル化の象徴だよなあ」というイメージを思い浮かべるかもしれません。
ある人は、「アメリカ経済が日本の株式市場に及ぼす影響」について思い浮かべるかもしれません。
ある人は、「グローバル企業は、利益をたくさんあげているのに全然税金を払っていない!」とお怒りになるかもしれません。
ある人は、「新宿区は外国にルーツのある方たちが区民の10%以上を占めるんだよなあ……」と思われるかもしれません。
しかし、AO入試で国際系の大学、学部を志望している受験生に「グローバル化って何?」と聞いても、「世界的な……?」といった浅い答えしか返ってこないのは、めずらしくもなんともありません。
推薦入試全般にいえますが、特にAO入試の場合、ご家庭での語彙力アップは喫緊の課題です。
語彙力アップについては、こちら不登校・勉強嫌いの中学生・高校生が最初に伸ばすべきは、「国語力」!をご覧ください。
ご家庭でいかに楽しく「裏打ち力」をアップさせるか
「裏打ち力」を上げるために、情報収集の方法、語彙力をご家庭でアップさせるコツは、「楽しさ」です。
子どもたちは自分が楽しいことであれば次々に調べ、知識を蓄積していきます。
「あんた、国際学部行きたいって言ってるのに、〇〇も知らないの!?」なんて、怒っては決していけません。
そうでなくても、受験を前に「不安」になっているお子さんを「恐怖と不安」で駆り立てるのはご法度ですので、お気をつけください!
ご家庭で「裏打ち力」を上げるために、情報収集の方法、語彙力をご家庭でアップさせるときは、ネガティブな指摘はなくてよいと思います。
目標達成しているかどうかは、子どもと話をしている中で、お子さまが何回「ヤバーい!」と笑顔で言ってくれるかで分かります。
ぜひ、ご家庭で「この言葉の意味ってこうなんだ」「あ、この情報って、面白いね!」とワイワイ楽しくやっていただきたいと思います。
AO入試では、まさにそのような「自分の好きなものを学ぶことに充実感を感じ、知識を蓄積していく」主体性のある学生を求めているのです。
入試に関する話題をお子さまと話すのにハードルを高く感じられる保護者さまは、まずはご家庭での雑談量を増やすことを意識してみましょう!
こちらの記事も、ぜひご覧ください。
ビーンズに相談されたい方は、こちらから。お気軽にお問い合わせください!
【ビーンズ流】総合型選抜(旧AO入試)の対策について
総合型選抜(旧AO入試)の対策についての記事はこちらからご覧ください!