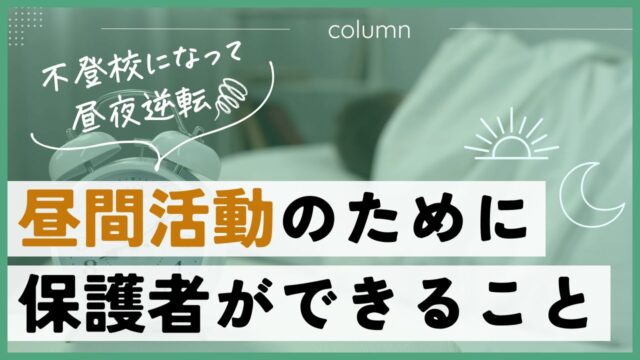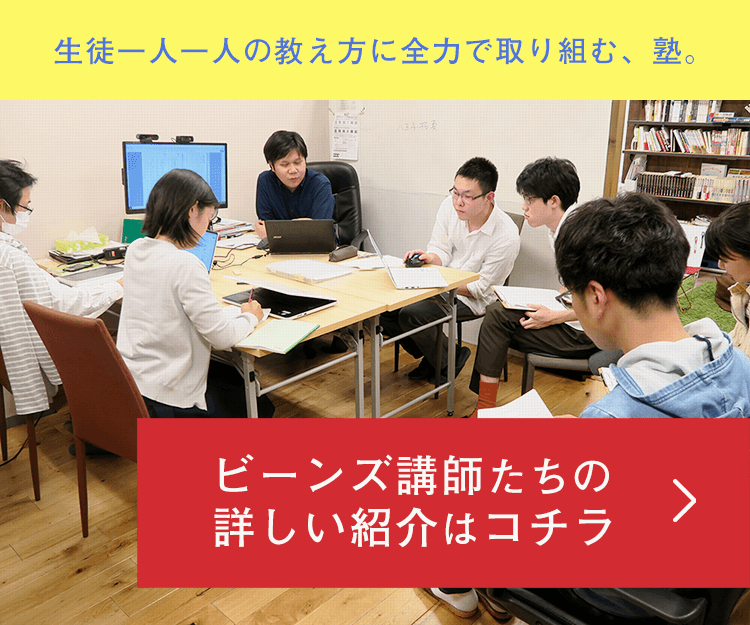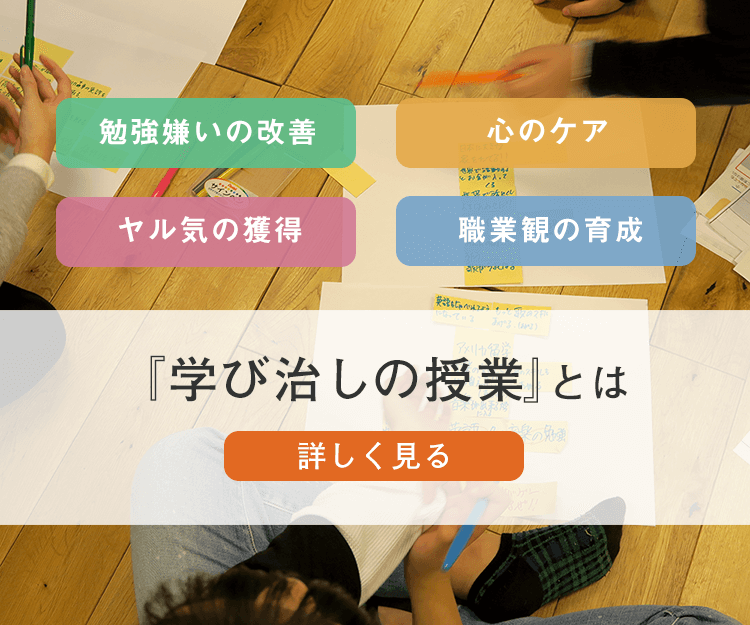不登校になって昼夜逆転した中学生・高校生。子どもが昼間活動するために保護者ができること
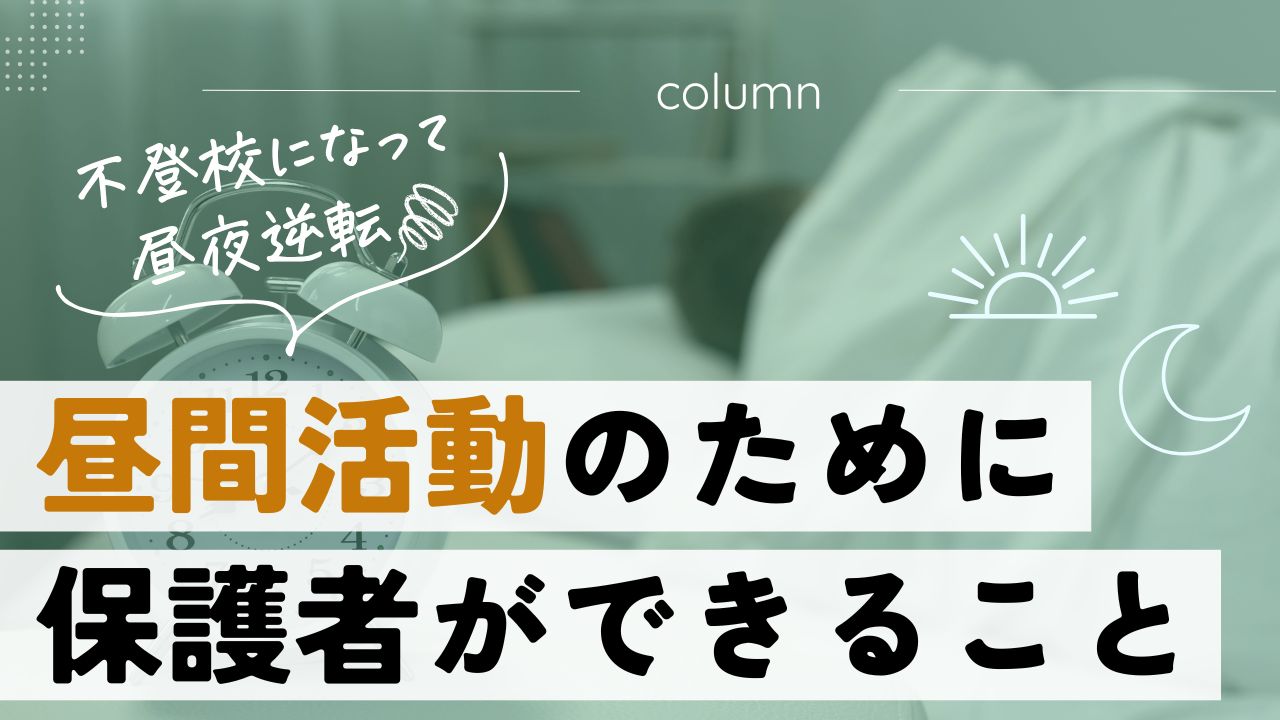
今回のテーマは、中学生・高校生のお子さんの「昼夜逆転」。
不登校になったお子さんの保護者さまから受ける相談の多くに、「子どもの昼夜逆転」という問題が共通して見受けられます。
本記事では、不登校になった子どもが昼夜逆転・夜型の生活になって朝が弱くなってしまった場合に、保護者さまがとるべき行動についてビーンズの代表の塚﨑がお話させて頂きます。
本記事の前提となる「親の見守り力」について詳しく知りたい方は、入塾待ち100人の不登校支援専門塾が解説する「我が子が不登校になったら見守るだけでいいのか」問題(解説動画つき)をご覧ください。
もくじ
不登校になって昼夜逆転した中学生・高校生。子どもが昼間活動するために保護者ができること

まずはお子さんの状態を見極めよう!
お子さんが昼夜逆転してしまった時は、まずはお子さんの状態を正しく見極めるようにしましょう。
朝が弱くなってしまったお子さんの特徴は、大きく2種類に分かれます。
朝が弱いお子さんの状態は大きく2種類!
1.好きなイベントの時は、朝きちんと起きられる状態
2.好きなイベントの時でも、どうしても起きられない状態
好きなイベントとは、たとえば買い物やお出かけなど、外でのアクティビティのことです。
学校に行くことは難しくても、友達と遊びに行く予定だったり、家族で旅行をしたり……
そんな楽しい予定の時にきちんと起きられるお子さんの場合、ちゃんと手順を追った対応をすれば、生活リズムも改善していきます。
ただし、好きなイベントがあっても、どうしても起きられないというお子さんに対しては、無理に改善しようとなさらないでください。
この場合、スリープクリニック(睡眠外来)など、医学的な相談も視野に入れていいかもしれません。
まずはお子さんがどちらのタイプなのか、慎重に見極めましょう。
生活改善のステップバイステップ!
楽しい予定の時は、朝が早くても起きられる子どもたち。
そんな彼らが、いざ学校があると起きられなくなってしまう理由は、ほとんどの場合、ストレスが原因となっています。
「学校に行かないといけない」
「学校で勉強をしないといけない」
「みんなと同じように学校へ行かないといけない」
そういった考えが悩みとなって頭の中で大きくなってしまい、体と心のバランスを崩して朝に起きることができなくなってしまいます。
やがて昼に起きて、夜に眠れなくなり……と、悪循環に陥ってしまいます。
そんな時、どのように改善していけばいいのでしょうか。
以下がポイントです。
生活改善をするための4ステップ
STEP1.子どものストレスを減らす
STEP2.早起きは少しずつ
STEP3.生活リズムが戻ってきたら自尊心を回復
STEP4.夜に寝られるよう工夫する
一気に状況を変えようとするのではなく、ステップバイステップでゆっくりと状況を改善していきます。
STEP1.子どものストレスを減らす
特に不登校のお子さんは、朝に強いストレスを感じていることが多いと思います。
それはお子さんは「学校へ行かないといけない」と強く思っているからです。
しかし、起きると「学校・通学」という現実と直面しないといけません。
つまり一部のお子さんにとって「起床=ツラい現実と戦わないといけない」という構図になっているのです。
さらに、そこへ保護者さまが「みんなと同じように学校へ行かないと将来真っ暗だよ!」といった追い打ちしてしまうと、お子さんはさらにストレスを感じてしまい、ますます朝起きることを嫌がるようになってしまいます。
そのようなことにならないよう、保護者様は学校へ行くことを強要しないようにしましょう。
代わりに、「明日は昼に出かけてみようか」など、お子さんが起きた後、楽しみになるような外出イベントを予定に入れるなどしましょう。
まずは、お子さんが「朝起きるといいことがある!」と認識してもらうことが大事です。
STEP2.早起きは少しずつ
「明日から毎日7時起きにしなさい!」といったように、高い目標を掲げても長続きしません。
それどころか保護者さまの言葉にストレスを感じてしまい、余計に起きれなくなってしまうかもしれません。
また、親の言う通りにできない自分自身にもストレスを感じて、「どうせ自分はダメ人間だ」というように、さらに自己否定感を強めてしまい、悪循環になってしまいます。
遅寝遅起を改善する際は、「昼起きを少しがんばって10時起きにしよう!」など、ちょっとずつ進めるようにしましょう。
また、状況改善している途中で、お子さん本人が
「明日から、僕は生まれ変わる!毎朝6時に起床して勉強する!」
と言ってくることも「あるある」です。
そんなときは「(まったく)期待せず、でも応援する」という姿勢が大切です。
そもそも人間の生活習慣がある一日を境にガラッと変わるなんてことはないのですから、6時起きだ!と言っていたお子さんが結局昼過ぎに起きてきても驚く必要も、落胆する必要もありません。
初めから期待してはいけないのです。
また、「6時に起きるって言ったのに!」なんて、揚げ足を取ることはやめてくださいね。
では、どうするか?
「もし早起きしたら、一緒にご飯たべようか」「一緒に朝、カフェ行くか」のように、お子さんの早起きという挑戦を応援しているという態度をとってください。
思春期のお子さんであれば、朝起きても実際に親とご飯食べることはないかもしれません。
だとしても、こういった一言をかけることで、お子さんは「あ、応援されてるな」と内心嬉しいものです。
不登校になったお子さんにとって、早寝早起の大きな障害は、「通学しなくてはいけない」という脅迫観念です。
「学校に行きたくないな……」と思って夜に寝られず、「学校に起きないといけない……」とストレスに感じるから朝に起きられません。
保護者さまが最優先すべきは、「生活リズムを改善させよう」ではなく、お子さんのストレスを緩和することです。
そして「朝起きたら、楽しいことがある!」とお子さんに思ってもらうことです。
この2点、ぜひお忘れなきようお願いします!
STEP3.生活リズムが戻ってきたら自尊心を回復!
不登校になって、「学校に行けなくなってしまった自分はなんて情けないやつだろう……」と、
自尊心や自己肯定感の少なくなってしまったお子さんにとって、昼間に起きているのは相当につらいことです。
なぜなら、(性格が真面目なお子さんほど)皆が通学している学校生活を送っているとき、自分だけ社会から仲間はずれになっているような疎外感を強く持ってしまうためです。
こんな時、どうすればいいか。
まずは、「今は学校に行くことが難しい状態だし、通学してもいいし、しなくてもいい。
それより、学校に行かない時間を使って、体力をつけたり、自分の好きなことをやるようにしよう」と思ってもらいましょう。
昼間起きていることにポジティブな意味づけをしたほうが、多くのお子さんは昼間にきちんと活動できるようになっていきます。
STEP4.夜に寝られるよう工夫する
お子さんのストレスに感じる心をほぐす方法は前述の通りです。
しかし、生活リズムを改善するためには、結局のところ「早寝」ができないといけません。
お子さんに限らず、大人だって朝方まで活動したら、翌日に早く起きることは難しく、健康も崩してしまうからです。
一説には、22時~午前2時が眠りのゴールデンタイムと呼ばれて、この時間に寝ると、成長ホルモンが出て、体力の回復ともに、心理的ストレスも緩和されやすいとされています。
このゴールデンタイムに睡眠をしっかりとるためには、それまでの間に、きちんと疲労して、眠るための工夫をしておくことが重要です。
【コラム】ゴールデンタイムに寝るためのコツ
ごくごく一般論ですが、ビーンズでお勧めしている寝る前のルーチンです。
1.頭を使う
20時くらいまでに、読書をしたり、ちょっと問題を解いてみたり、「考える」という行動をしてみましょう。
2.昼間に体を使う
夕方~夜の間に20~30分ほど散歩で良いので、近所を歩きます。
身体を疲れさせて、体温を上げる時間を持つことは睡眠において重要となります。
3.寝る前にお風呂
一日のリズムを整える上で、お風呂は欠かせません。
睡眠の2時間前までに、湯船に浸かって、しっかり暖まって体温を上げる。
その後、体温が下がったところで布団に入るようにすると眠りにつきやすくなります。
このお風呂を習慣化させただけでも、一気に寝つきが良くなったお子さんもいますので、おすすめです!
さらに、夜特に22時以降、お子さんにパソコンやスマホに触れさせないようにすることも重要です。
ブルーライトは目から脳を刺激して、睡眠の妨げとなってしまうからです。
「スマホ・ネットは22時まで」と、夜の間だけルールを徹底することも大事です。
この時、事前交渉なしで取り上げてしまう・取り上げたまま翌日も返さないような行為をすると、
お子さんのストレスが膨らんで、かえって状況が悪化してしまいます。
まず、「スマホ・ネットを制限するのは、生活リズムを整えるため」だとお子さまへ伝え、
時間をかけて交渉した後、夜の間だけ使用を制限するという約束をきちんと交わすようにしましょう。
詳しくはこちらの記事もご覧ください
まとめ:生活リズムの状況改善の流れ
ビーンズの考える状況改善の流れと保護者さまがやるべきことをまとめると、以下の通りです。
状況改善の流れ
・お子さんがご自宅で楽しく活動できるようになる
・お子さんが昼間に楽しく活動できるように働きかける
・健康的な生活と、抑圧しない環境を作り、お子さんの自尊心を回復させていく
・自尊心が回復すると「これからどうしようかな」と進路を考えるようになる
・お子さんが自分の状況を改善したいというサインが出してきたら、保護者さまと一緒に進路を考えていくようにする。
(この時、復学できそうなら復学でも良いですが、また揺り返す危険もありますので、ビーンズとしては、このタイミングでお越しいただけるのがベストと思います)
昼夜逆転改善のために親がすべきこと
・お子さんとの雑談を増やす
・お子さんから学校の是非を聞かれたら「学校は行ってもいい、行かなくてもいい」という姿勢を示す
・お子さんが朝に起きる「動機」をつくる(朝ごはん、朝カフェなど)
・お子さんが昼間に活動する「動機」を提案する(ランチ、映画、野外でのアクティビティなど)
・生活リズムが改善して、お子さんが「なにかしなくちゃ」と考え出すサインを見極める
・お子さんと「より昼間の時間が豊かになるにはどうすればいいか」を一緒に考えていく
まとめ 最初の一手は「お子さんとの雑談量を増やす」。そして"無料相談"!
生活リズムの乱れと、不登校の問題は、密接な関係にあります。ただ、ほとんどの場合、どちらの改善方法も同じことです。
昼夜逆転になってしまったお子さんにとって現実世界はストレスにあふれています。
さらにお子さんへストレスをかければ、お子さんはストレス源のない夜の世界へますますはまり込み、昼間の世界から逃避してしまいます。
ポイントはお子さんのストレス源を減らし、昼間の楽しさを増やしていくことです。
ご自宅だけでもお子さんにとってストレスのない・楽しみがある世界にすること。
そのための最初の一手は、お子さんとの雑談量を増やし、お子さんにとって「ご家庭を絶対安心の場」にしていくことです。
「【中学生・高校生のお子さんが不登校・引きこもりになったら……】まずは親子の会話量を増やそう」の記事で、お子さんにとって「ご家庭を絶対安心の場」するコツをまとめています。
また、この記事に書いてあるアドバイスは『ビーンズメソッド』という”悩める10代”へのサポート方法に基づいています。
「ビーンズメソッドってなに?」という方は、まずコチラの動画をご覧ください。
「情熱大陸」「カンブリア宮殿」などの各種メディアで著名な花まる学習会代表 高濱正伸先生、教育ジャーナリストおおたとしまささん
このお二方とビーンズ塾長の長澤が、”悩める10代”の現状、そしてビーンズメソッドの考え方について講演したときの様子です。(ダイジェスト版)
また、おおたさんには、「ガラスの十代のトリセツ/ビーンズメソッドに学ぶ」と題し、ビーンズメソッドの基本的な考え方についてお話しいただいています。
そして、ビーンズも取材いただいた『不登校でも学べるー学校に行きたくないと言えたとき』(集英社新書)。
さらに、講談社FRaUさんでは、ビーンズメソッドのエッセンスを端的にまとめていただきました。こちらもぜひご覧ください。

『10代の心をフリーズさせるもの…不登校専門塾が教える「大人がやってはいけない」こと』
『生きる重荷を軽くしたい…不登校専門塾が提案する“子どもを幸せにするための法則”』
また、本記事の前提となっている「親の見守り力」について詳しく知りたい方は、入塾待ち100人の不登校支援専門塾が解説する「我が子が不登校になったら見守るだけでいいのか」問題(解説動画つき)をご覧ください。
一人で考えることがしんどくなったら、無料相談へ
ここまで長い文章をご覧いただいている保護者さまは、本当にお子さんのことが心配なんだと思います。
ご心配のあまり「ちょっとでもいいから学校へ行きなさい!」、「このままで、将来どうするの!?」
と(頭では)効果がないと分かっていても感情的になってしまう……
それも保護者さまが本気でお子さまのことを心配されているからこそ。
仕方のないことなのです。
そういった場合、保護者さまだけで状況改善を目指すのではなく、ビーンズの"無料相談"をご利用することをおすすめします。
お子さんに関するお悩みを私たちへお話しするだけでも気持ちが軽くなります。
またビーンズのお子さんたち・ご家庭の豊富な事例から、
〇ビーンズの生徒たちの"昼夜逆転"あるあるな事例とその対処法
〇ビーンズの生徒が昼間の時間を楽しめるようになったキッカケ
〇ご家庭で、保護者さまにしていただきたいこと
など、具体にお話しをさせていただきます。
今の状況を上向かせるにはどうすればいいか、私達と一緒に考えていきませんか?
無料相談フォーム
【ビーンズからのお願い】
お電話でのお問い合わせをたくさんいただいておりますが、リモートワーク推進のため、
お電話でのお問い合わせはなるべく避けていただきたくお願い申し上げます。
(折り返しお電話できない場合もございます。)