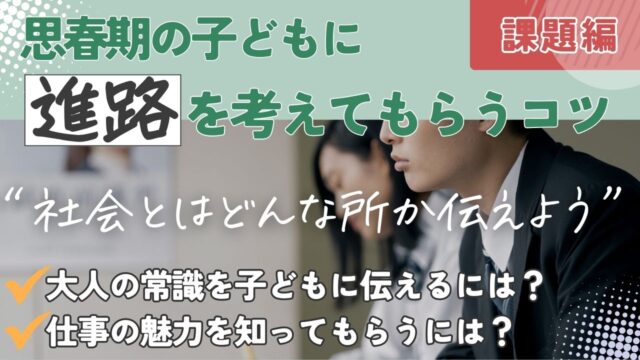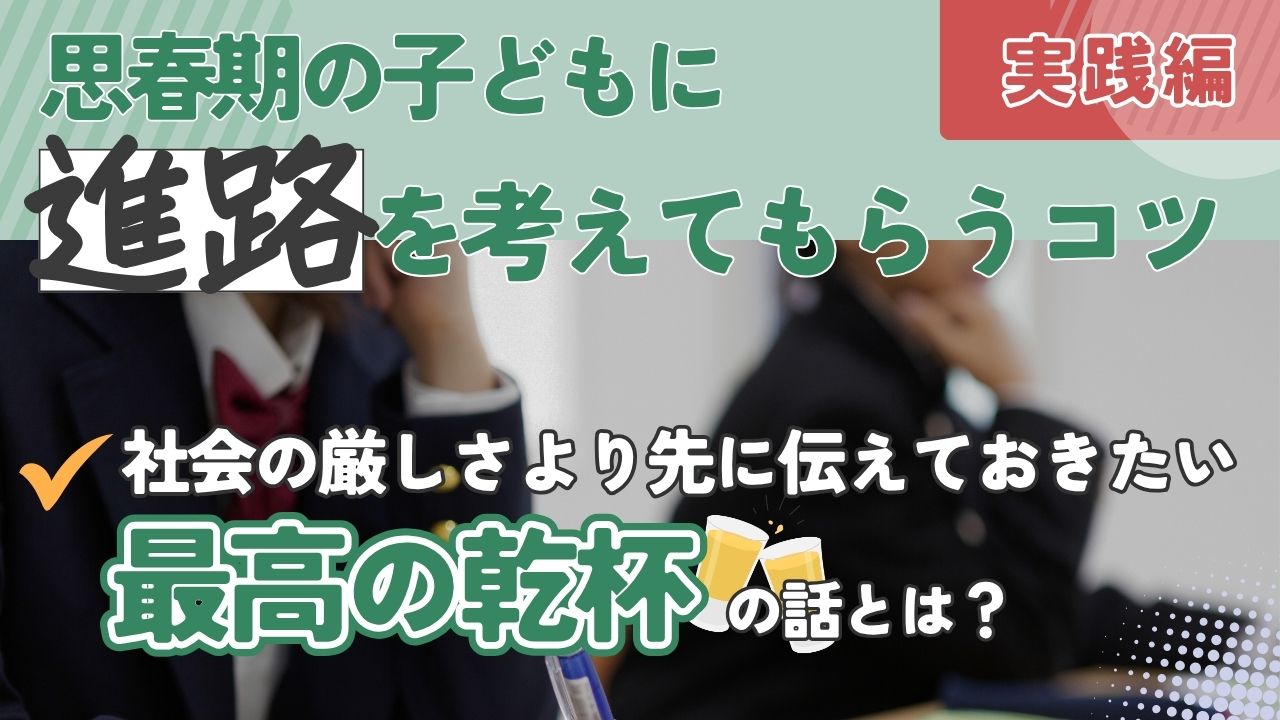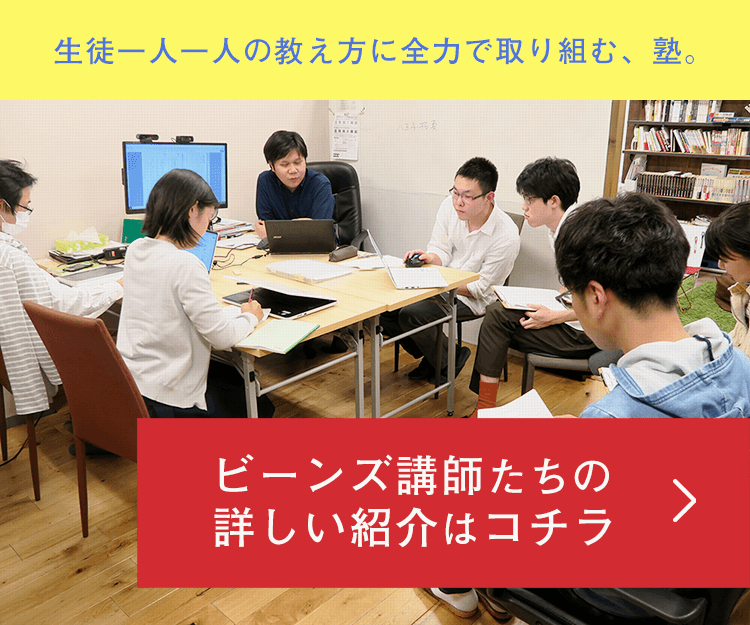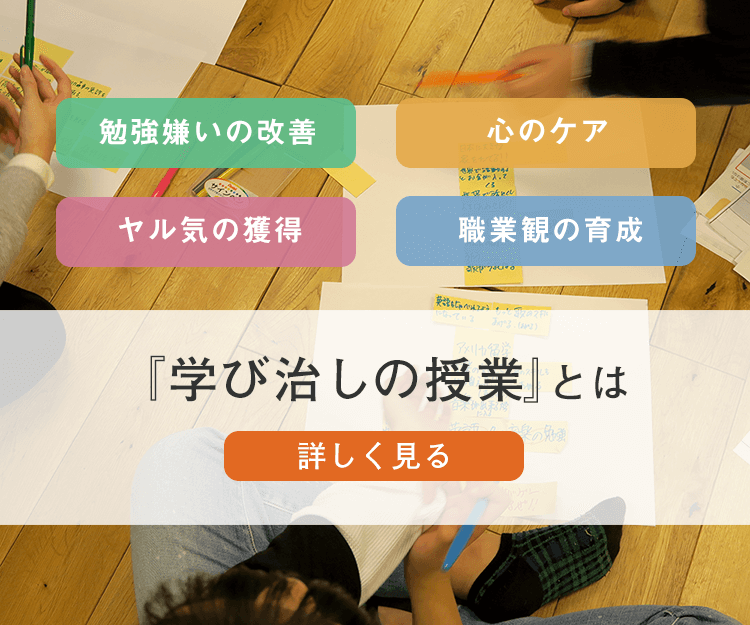【中学生・高校生向け】家庭でできる 思春期以降の子どもたちに進路を考えてもらうコツ 課題編
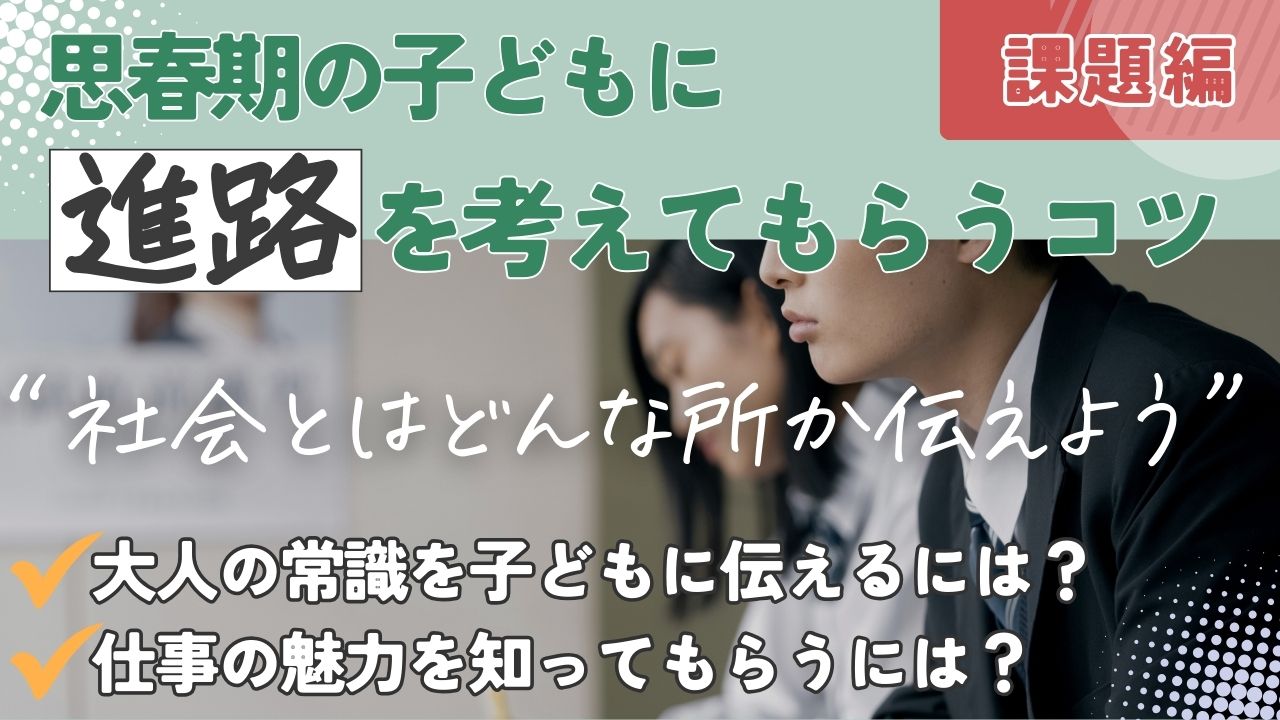
今回の記事では、不登校・勉強嫌いな中学生・高校生たちが進路を考えていくためには「ご家庭で職業観を“楽しく!”育むことが大事」という内容で、
『ビーンズメソッド』に基づいた中学生・高校生たちの進路観、そしてお子さまに進路を考えてもらうための、ご家庭での声掛けのコツを代表の塚﨑がお話しします。
不登校・学校嫌い、でも進路を決めないといけない…そんな「悩める10代」のお子さまを持つ保護者さまへ、ぜひお読みいただきたいです。
※本記事は2021年に公開した内容を加筆し再公開しています。
「ビーンズメソッドってなに?」という方は…まずはこの動画をご覧ください。
「情熱大陸」「カンブリア宮殿」などの各種メディアで著名な花まる学習会代表 高濱正伸先生、教育ジャーナリストおおたとしまささん
このお二方とビーンズ塾長の長澤が、”悩める10代”の現状、そしてビーンズメソッドの考え方について講演しました。
おおたさんには「ガラスの十代のトリセツ/ビーンズメソッドに学ぶ」と題し、ビーンズメソッドの基本的な考え方についてお話しいただいています。
そして、ビーンズでの取材内容を『不登校でも学べるー学校に行きたくないと言えたとき』(集英社新書)に掲載いただきました。
また、講談社FRaUさんでは、ビーンズメソッドの内容を端的にまとめていただいています。こちらもぜひご覧ください。

『10代の心をフリーズさせるもの…不登校専門塾が教える「大人がやってはいけない」こと』
『生きる重荷を軽くしたい…不登校専門塾が提案する“子どもを幸せにするための法則”』
塚﨑 康弘(Tsukazaki Yasuhiro)
大分県中津市出身。学校嫌い・科目勉強嫌いを乗り越え大学進学するものの大学1年次で不登校。
大学卒業後、約2年間のニート期間を経た後、塾講師・家庭教師として活動しながら「学習支援塾ビーンズ」を設立。2015年に法人化し代表を務める。
好奇心旺盛だけど無趣味。こだわり多いけど毎日白Tシャツ。早稲田大学 人間科学部卒。
■インタビュー/詳しい自己紹介
・『東京都創業NETインタビュー』に代表・塚﨑が掲載されました!
・オデッセイ コミュニケーションズさまに学習支援塾ビーンズ代表・塚﨑がインタビューされました!
もくじ
【中学生・高校生向け】家庭でできる 思春期以降の子どもたちに進路を考えてもらうコツ 課題編
…「子どもが進路について全く考えようともしないんです」
…「進路の話をしようとすると、いつも部屋にこもってしまいます」
…「これから、本人はどうするつもりなのか? 子どもの気持が分からないんです」
夏が過ぎて、ツクツクボウシの声も少しずつ遠くになっていくころ、保護者さまから このようなお声が多くなります。
そこから何カ月か経つと、今度は中学生~高校生の生徒たちからも
「もう、僕の将来は終わっているんです」
「社会に出るのが怖い。どう考えても生きている気がしない」
「勉強して、ちゃんとした人生にならないといけないのに、できない」
そういう声を聞くようになります。
進路については、保護者さまも、子どもたちも焦ります。
そして、焦りからくる恐怖と不安でいっぱいです。
特に不登校・ひきこもり・勉強嫌いになってしまっている中学生・高校生の子どもたちは、
「自分は親の希望する将来をを実現できない」と感じると
↓
「自分はダメなやつ=今後も何をやっても、お先真っ暗」
と、自尊心が下がり、自身の進路について諦めてしまい、にっちもさっちもいかなくなってしまう…といったパターンにはまってしまうのです。
この記事では、中学生・高校生の子どもたちがなぜ進路について悩むのかについて課題を明らかにしていきます。
多くの中学生・高校生は「進路のことを考えるのが不安」
まず前提となるお話をします。
中学生・高校生の子どもたちは、不登校であるなしに関わらず、社会の明るい面ではなく、暗い面を多く見ています。
不登校であるかどうかにかかわらず、そもそも中学生・高校生たちは進路のことを考えると不安になります。
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ・一般社団法人全国高等学校PTA連合会合同調査「第8回高校生と保護者の進路に関する意識調査2017年報告書」によると……
高校生のうち、「進路を考えると不安」と答えたのは70%を越え、
逆に「進路を考えると楽しい」と答えた割合は約20%でした。
保護者さまのなかには「若者が将来のことを考えるのはいつの時代だって不安じゃないか!」と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし!
私が高校生だった2003年の調査(「高校生と保護者の 進路に関する意識調査」)では…
進路を考えると不安が44%
進路を考えると楽しいが34.5%
とほぼ拮抗していることが分かります。
<保護者さまへお願い 昔の若者像をあてはめないで>
同じ「高校生」でも、保護者さまが高校生だったころと、今の高校生は、進路や、職業観へのマインドは大きく変化しています。
以下のデータをご覧ください。
私たちが高校生のころに比べ、明らかに現在の高校生の方が進路のことを考えることについての不安感が増しています。
保護者さまが「自分が高校生だったころ」を思い返して当てはめようとしてはダメなのです。
●なりたい職業がある
2003年の調査「約70%がある」
⇓
2017年の調査「55%」(なお男子は50%以下)
●進路を考えると不安
2003年の調査「約44%」
⇓
2017年の調査「72%」(約1.6倍)
●進路を考えると楽しい
2003年の調査「約34.5%」
⇓
2017年の調査「23%」(約4割減)
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ・一般社団法人全国高等学校PTA連合会合同調査
「高校生と保護者の 進路に関する意識調査」 (2003)
「第8回高校生と保護者の進路に関する意識調査2017年報告書」より作成
不登校の中学生・高校生が進路に絶望しやすい理由

不登校の中学生・高校生たちは
「自分以外のみんなは普通に学校に行って勉強している」
「それができない自分に明るい将来はない。お先真っ暗だ」
というような、悲観的な考えにとらわれている場合が多くあります。
(この子どもたちがとらわれている「普通」の中身について詳しくは「不登校の子どもたちが信じる「人生の先入観」 を外す!「普通を外すワーク」」をご覧ください)
保護者さまに面談でよくお話しする、ビーンズで有名な小咄(こばなし)にこういうものがあります。
あるとき、大学一般受験で「とりあえずMARCH」(ビーンズでは「とりマ」と呼んでいます)を目指している高校三年生男子が参考書を机の上に出したまま、真っ青な顔で硬直していました。
彼に話を聞くと「勉強がつらくてつらくて、でも自分はMARCHに行かないといけない」と言うんですね。
以下は実際にあった講師と生徒とのやりとりです。
[コラム]勉強した先に暗い将来しか見ていない例「大手広告代理店エピソード」
講 師:どこらへんで、MARCH選ぼう!ってなったんだっけな
生 徒:MARCHに行かないと大企業へ行けないんです。
講 師:ほうほう。大企業って、例えばどこよ?
生 徒:(真っ青な顔で)D…(大手広告代理店)
講 師:念のため聞くけど、どのD…なの?
生 徒:あの…… 過労死の……。
講 師:その大手広告代理店って何してる会社か知ってる?
生 徒:知らない。ただ、お金はありそうだなって。
講 師:なるほどね。その大手広告代理店に代表される大企業に行けなかったら、君はどうなるの?
生 徒:負け組になって、職を転々して、最終的にホームレスになると思う。
講 師:生活保護は?
生 徒:それは無理。どうやったらいいか分かんないし、恥。ホームレスになったら餓死。
つまり、その生徒のキャリア観とは…
MARCHに行けなければ大企業に行けず…
大企業に行けなければホームレスになって餓死してしまい…
さりとてMARCHに入学し大手企業に入ったとしても、最後は過労死する(まで追い込まれる)
という救いのない真っ暗なものなのです。
そこで「ホームレス餓死コース」と比較して、ややマシな「 大企業過労死コース」に入るために、MARCHへ向けて頑張って勉強しようという筋書なのです。
努力した先にも真っ暗な将来が待っている中で、まだましな将来にむけて「恐怖と不安」をエネルギー源にして自分を駆り立てて、好きでもない勉強を続ける…
常人だと耐えられないですよね。
なぜ、子どもたちは、このような悲観的な考えにとらわれているのでしょうか。
なぜなら、子どもたちは社会の明るい面ではなく、社会の暗い面の情報を多く集めてくるからです。
なぜか。それは子どもたちの周りにあり、子どもたちが摂取する情報には、圧倒的に暗い話題が多いからです。
例えば、ニュースを見ると新聞もTVもネットニュースでも暗ーい話題が多いですよね。
特にネットニュースでは、SNSや、動画サイト、まとめサイトなどで暗い話題や誰かの失敗談が目白押しです。
政治経済の話題が好きな子どもにも、YouTuberが好きな子どもにも、それぞれの子どもの、それぞれの嗜好に応じた暗ーいニュースがネットにはたっぷり用意されています。
特に不登校の中学生・高校生はTwitterなど各種SNSで暗いニュースばかりを摂取しています。
そして、SNSでは“不登校” “(学校の)勉強ができない”ことへの「恐怖と不安」を煽り立ててきます。
ネット上に跋扈する暗ーい世界観の例
・出身大学(校)から勝ち負けに二分される。
・負けたら社会からトコトン食い物にされる。(不登校は学校に行っていないので負けており、食い物にされる)
・勝つためには、覚悟をもって朝から晩まで徹底的に頑張らないといけない。
・勝ち組になると、デカくてホワイトな会社に入り、高給で余裕のある生活。
・なお勝っても負けても自分の好きなことはできない。会社の指示に従うのみ。主体性は求められない。
どこの「タワマン小説だ!?」と思う方もいらっしゃると思います。
が、こういった世界観をつくりあげるに充分な情報を中高生たちは大量に摂取しているのです。
上記の「暗ーい世界観の例」の中には確かに“正論”の部分もあります。
しかし、かなり極端(グロテスク)な世界観ですよね。
(当たり前ですが)社会の中で活躍している不登校経験者も少なくありません。(私自身もそうです)
また、不登校に限らず、世の中で活躍している殆どの人が、なんらかの挫折を経験しているはずです。
ただ、中学生・高校生の子どもたちには、そういった挫折経験があって活躍している人たちと生活の中で出会うことがありません。
また「4つの時期」の「挑戦期」でない子どもたちだと、仮に挫折経験があっても活躍している人のストーリーを知ったとしても「その人は特別。僕はそんな努力はできない」と、そのストーリーを受容しづらいのです。
あと、重要なポイントが、先の生徒の話に出てきた「大手広告代理店」について、子どもたちが何を知っているかという点です。
確かにブラックな働き方をしている人、しんどい思いをしながら働いている人もいた(もしくはいる)事実はあったとして。
それ"だけ"ではないはずですよね。
自分の仕事に誇りを持っている方、
素晴らしいサービスや製品を生み出している方、
ライフワークバランスをとりながら、自分の時間、家族との時間を大切にされて仕事をされている方…
逆に自らの成長や収入のために、ライフワークバランスをかなぐり捨てて、仕事に打ち込んでいる方…
いろいろな方が、さまざまな働き方をされているはずです(特に大企業は)。
しかし、上記の生徒はそもそも、その大手広告代理店がどんな仕事をしているのか? どこにあるのか? すら知りませんでした。
この「子どもたちが社会について正確なことを知らずに、ただただ不安を掻き立てられている」現象を、私は「子どもたちがすりガラス越しに暗闇を見る」と呼んでいます。
子どもたちは社会についての正確な情報を持てないまま、タワマン小説的な、グロテスクなほど悲観的な情報を摂取し続け、(すりガラスの越しの先にぼうっと映る虚像を見て)「社会は暗闇なんだ」と断じてしまうのです。
この「子どもたちがグロテスクな世界観を摂取している」という現象は、保護者さまの努力だけでは解決できません……。
仮に保護者さまが
・保護者さまは上記のようなキャリア観は持っていない
・保護者さまが上記のようなキャリア観とは真逆の生き方をしている
例:偏差値にとらわれないで学校を選んだ
例:自分の好きなことでしっかり稼いでる
といった場合でも油断は禁物です。
思春期の子どもは一人の時間が多くなります。そしてスマホを持っています。
まして、不登校の中学生・高校生には、あまりある時間があります。
その時間で上記のタワマン小説的・悲観的・グロテスクな内容のキャリア観を摂取し、染まってしまう可能性があるのです。
中学生・高校生たちの社会は狭い
なぜ、可能性がたくさんある中学生・高校生たちがこのようなタワマン小説的・悲観的・グロテスクな内容の考えにとらわれているのでしょうか。
それは中学生・高校生たちの世界・社会が狭いからです。
子どもたちは、大人に比べて非常に限られた社会や職業に関する情報しか持っていません。
例えば、就職活動をしている大学生であっても「プライム上場企業をあげられるだけあげてください」と言ったら、すぐ詰まってしまう人は少なくないと思います。
就活活動をしている大学生であっても、彼らにとって知名度のある業界以外だと、どんな有名企業であっても名前も知らない…そんなことは珍しくありません。
もちろん、(大学生たちにとって)名の知れた企業であれば…もっと具体的いうと…彼らは世界一の自動車メーカーの名前を間違うことはありません。
が、そのメーカーに重要な部品をおさめている世界的な有名な大企業(もちろん上場企業)の名前は知らない…ということです。
その点、大人であれば、
「あの会社は、あの業界の大手だよね」
「あの業界のトップ企業のグループだよね」
と半ば常識として知っています。
もう一つ例をあげると…
「ゴリゴリ働いて高収入!」
「OBたちは起業しがち」
…といったその会社のOBたちがYouTuberになりがちで、露出が多く(良くも悪くも)大学生たちの間で有名な(ネタにされている)機械メーカーは知っている場合が多いのです。
が、そのメーカーより仮に会社規模や売り上げは大きくても、知られていない会社はとことん知らないのです。
子どもたちは職種や働き方についても知らない
同様に、子どもたちは、職種や働き方についても具体的なイメージを持っていないことが多いです。
つまり、営業や経理についてはフワっと知っていても、総務部や人事部になると想像がつかなくなる…という状況が生まれます。
もっと言えば、会社で勤める以外の働く選択肢(例えば個人事業主でフリーランスとしてお金を稼いでいくとか、自分で起業するとか)は知らない…という場合がほとんどです。
働く内容、そして働き方についての、知識も肌感覚も絶対的に足りていません。
大人であれば、
「大企業からフリーランスになりました・起業しました」
「育児の傍らで、個人事業主として個人で仕事を請けています」
という方々に出会う機会は、社会の中で珍しくはないはずです。
でも、子どもたち(何度も言いますが、大学生もです)には、その経験は絶無なわけです。
もちろん、彼らも大企業に就職するメリットというのはフワッと分かっています。
分かってはいるんですけども…
それは、
「なんか昇給するっぽい」
「なんか給与がよいんでしょ?」
といった、それくらいの解像度であって、「この企業の〇〇の福利厚生制度は、××という点がよくて…」という解像度にはなりえないのです。
ましてやフリーランスとして活動したり、独立起業するときのデメリットやコスト、そしてポジティブな可能性…そういったことは全く知りません。
ざっくりいうと、
「大企業以外で勤めることは、怖い・リスキー」
「フリーランスで独立すること・起業すること=清水の舞台から飛び降りること」
「だけど、一括千金で儲けられるらしい。(だけど)上場、それはナニ?」
という…ものすごい、漠然とした印象を持っている場合が多いのです。
学校教育でも社会を知る機会は少ない
そして、中学生・高校生たちにとっては、家庭と学校が世界・社会のすべてであることも少なくありません。
そのため、学校で何か挫折経験があると、子どもたちにとっては世界・社会から拒絶されたと感じられるのです。
ここでのポイントは、「学校を不登校になった・学校の勉強をしない……」そんな子どもたちも、
本心では「学校に戻らないといけない」「受験勉強しないといけない」という「恐怖と不安ベース」の気持ちを抱えています。
この「~しないといけない」という気持ちが、子どもたちのエネルギーを奪ってしまうです。
そんなエネルギーが枯渇しかけている中学生・高校生の子どもたちへ、保護者さまが
「(普通に)学校に行って、勉強して!」
「このくらいのレベルの進学先に行って!」
と恐怖・不安ベースで要請すればするほど、
世界・社会から拒絶されたと感じてる子どもたちにとって「絶対安心の場」であるべきご家庭で、お子さんは追い詰められていきます。
中には「恐怖と不安」で自分自身を駆り立てて頑張ろうとするお子さんもいます。
ただビーンズにくるお子さんの多くは「恐怖と不安」で頑張ろうとしても続きません。
そして保護者さまの視界からフェイドアウトして(自室に引きこもって)しまうのです。
さて、ここまで読んで、「うちの子は、学校へ通っているから大丈夫」「学校で職業観の授業があるから大丈夫」と思っている保護者さまもいらっしゃるかもしれません。
残念ですが、それは違います。
●公立中学では98%の学校で職場体験が実施されているが、その実施日は3日までが80%を越えている。
●公立普通科高校の約80%が職場体験を実施しているが、生徒の参加率は20%。
参照:国立教育政策研究所「平成29年度職場体験・インターンシップ実施状況等結果(概要) 」
わずか3日の職業体験。
これが多くの中学生・高校生たちに与えられた「職業観を育む時間」です。
また、その職場体験の内容についても、中学生・高校生たちの職業観が育つのか疑わしいものも多いのが現状です。
<公立中学校での職場体験 ビーンズの子どもたちの実例>
●スーパーマーケットの惣菜コーナーで弁当をひたすら並べ続けた
●区役所に赴き、放置自転車を回収する班に配属され、放置自転車の回収で職場体験が終わった
●運送会社で軽作業を行う職場体験に参加。最終日に生徒がどのようなスキルを身につけたら昇給するか総務部長に質問したところ、後に中学校教諭から「なぜあの場でお金のことについて質問したのか」と詰問された
学校に通っているとしても、そもそも中学生・高校生たちが「社会を知り、職業観を育てる機会は圧倒的に不足」しているのです。
さきほど「中学生・高校生の子どもたちにとって、家庭と学校が世界のすべて」と申し上げました。
「学校教育は、中学生・高校生の子どもたちに、社会を知る機会を充分に与えていない」と言い切ってしまっていいと思います。
つまり、お子さんに社会のなんたるかを知らせ、職業観を育てるためには、ご家庭での取り組みが非常に大切になってくるのです。
ご家庭で中学生・高校生の子どもに社会を知らせるコツは「同質から異質」「他人事・遠い将来」
さて、ここまで申し上げてきたように、
社会に明るい希望と展望を持ててない中で…
社会や業界・職種や働き方についての、不完全なごく限られた情報しか持てていない中で…
子どもたちが自分の進路を選ぼうと四苦八苦している様子を見ると
どうしても大人は
「子どもが、いろんな思い込みをしながら進路を選んでいるのでは…?」
「社会や働くことについて、とんでもない誤解や錯覚しているのでは…?」
と、心配してしまいます。
保護者が子どもから進路選びについての意見を聞いたときに、
ある業界の(大人からみたら)当たり前の情報を全然知らなかったり…
非常に偏った情報だけで社会をとらえていたり…
夢みたいなことばかり語っていたり…
逆に子どもが、
「働くことは絶望なんだ」
「社会には夢も希望もないんだ」
「できたらずっとニートでいたいんだ!」
と言っていたり…
そういう場面に直面すると、親として心配になってしまう…。
これは致し方ない事だと思います。
子どもたちが、
・持っている進路について考える情報が少ない中で、
・業界も業種も大企業の名前も(ましてやキラリと光る中小企業の名前も)知らない中で、
・そして、「働くということはどういうことか」ということも体感がない中で、
・仕事をすること、創業・起業すること、仲間と何かの価値を創出することの「厳しさとやりがい」を知らない中で、
子どもたちが、夢見がちな将来を語ったり、もしくは逆に「もうダメなんだー」というふうに塞ぎ込んでしまったりする…
そんな子どもの様子を見ていると、
「いやいや、ちゃんと現実をしっかり見て!」
「現実をしっかり見たうえで、冷静に自分の将来を考えて欲しい!」
と、焦ってしまうのは親として無理からぬことだと思います。
子どもの努力不足…というような問題ではない
ただ、大人がその焦りを子どもに直接伝えてしまうこと…これは避けていただきたいのです。
子どもたちが、先ほど申し上げた業界を知らないとか世界が狭いということは、構造的な問題です。
子どもの今までの生育歴の中で、
業界や業種を知り
職種による働き方を知り
働き甲斐や働くことの大変さを知る
…そういった機会を与えられていない中で、さらに、SNSなどを通して日本の暗い将来についての情報ばかり与えられて、その情報を(好むと好まざるに関わらず)摂取してしまった結果として、今の状態があるわけです。
これは子どもの努力だけでどうにかなる課題ではありません。
そこに対して、
「子どもが努力不足なんだ!」
「子どものスタンスが悪いんだ!本気じゃないんだ!」
と、結論づけて、子どもを追い詰めてしまうのは不条理だと思います。
また、仮に「子どもの努力不足」「子どものスタンスが悪い」というロジックで子どもを(追い)詰めても、子どもたちの行動変容には結びつきませんから不合理でもあります。
子どもの世界を広げていくキーワードは「同質から異質へ」「子どもの半径5センチメートル」
では、どうすればよいのでしょうか。
ビーンズでは、特に思春期以降の子どもたちには「子どもの世界を無理なく広げていく」ことが大事だと考えています。
キーワードは…
「同質から異質へ」
「子ども自身の半径5センチメートルを大切する」
子どもが持っている世界とは、子どもにとっての「当たり前」。
…言い換えると、子どもが内面化している「マナーやモラル」の複合体のことです。
大人が、それらを遠く飛び越えた子どもにとって異質な意見や正論を(いきなり)伝えてしまう事は避けて欲しいのです。
仮に、その正論が、大人にとっては当たり前な事柄であっても、子どもにとって異質な情報をどーんと突きつけて「これが世界の真実だ!」と言ってしまうと、子どもがフリーズしてしまいます。
例えば、さきほどの「夢見がちな子ども」の例で言うと…
子どもが「私はYouTuberになりたい!YouTuberになって稼ぎたい!」と言い出した時に
我々大人側は
・YouTuberになるために必要なスキルがあること
・YouTuberに限らず、あらゆる仕事で成功するには一定以上のメンタルのつよさ・レジリエンスが必要なこと
・ある程度の金額を売り上げていったら個人事業主、さらに売上があがってくれば会社を作ること、つまり法人化したほうが税金対策になること
…こういうことを大人側は、知識や経験測として分かっているわけです。
そして、そこのところに知識がない・経験がない子どもたちに対して、
「お前、動画を撮影して毎日アップロードしていく根気はあるの?」
「資材の購入費用はどうするの?税金対策はどうするの?」
といったところをバーンと伝えてしまいがちです。
…これだと子どもがフリーズしてしまう恐れがあり、よろしくありません。
そうではなくて(特に思春期以降は)子どもが持っている世界に配慮しながら、
子どもが情報や経験量を徐々に増やしていける機会を、子どものスピードに合わせて与えていく事が大切なのです。
ご家庭でできる! 無気力な中学生・高校生に進路を考えてもらうコツ 課題編 まとめ
大人は社会に出て「進路を考える大切さ」も「社会とはどのようなものであるか」も身をもって知っています。
そんな大人でも「これからの少子高齢化社会の中で、自分のライフプランどうするつもり?」といきなり聞かれても、すぐに答えられる人は少ないでしょう。
大人でも、将来のことを真剣に考えだすと、不安になったり、悲観的になったりする場合もあると思います。
なぜでしょうか。
【大人であっても、自分の将来を真剣に考えられないときは…】
「これからの社会の課題」について情報が足りない
「これからの社会の課題」について向き合うのが怖い
この2点が主な理由だと思います。
中学生・高校生のお子さんが進路を考えられない理由も同じです。
中学生・高校生が学校で習っていることは主に「科目の勉強」です。
学校では「問題の解き方・テストや成績の価値観・偏差値に応じた進路」などは教えてくれます。
しかし、それ以外のことになると、基本的には教えてくれません。
子どもからすると「進路を考える」ための情報が足りないのです。
そして、多くの中学生・高校生の子どもたちは自分の将来のことを考えるのに不安な気持ちがまさっています。
「情報が足りない」「将来のことを考えるのが怖い」…
大人が自身の将来を考えられない全く同じ構造が中学生・高校生にも存在するのです。
ですから、不登校や勉強嫌いの中学生・高校生が、いきなり自分の進路を主体的に考え出す…ことはありません。
にもかかわらず、
「将来や進路について考えて、決めろ」
「そして決めた進路に向けて本気になって行動しろ!」
といきなり言われたら、「無茶ぶり」です。
(無茶ぶりにせず)子どもたちに進路を考えてもらうよう促すための最初のステップは、保護者さまが「社会の魅力」「仕事の面白さ」を中学生・高校生のお子さんに楽しく伝えることです。
子どもたちは将来に希望を持つことで、状況を改善しようとするエネルギーを得て、自分の進路を主体的に考え始めることができます。
続きの記事で、保護者さまから「中学生・高校生のお子さんへ社会の魅力・仕事の面白さをどのようにプレゼンテーションすればいいか」より具体的なコツをお伝えします。
「そんなこといっても、親の言うことに、子どもがちっとも耳を貸してくれない……」という場合、子どもにとって「ご家庭を絶対安心の場」にすることが優先です!
子どもにとって「ご家庭を絶対安心の場」にする方法については、こちらの記事をご覧ください。