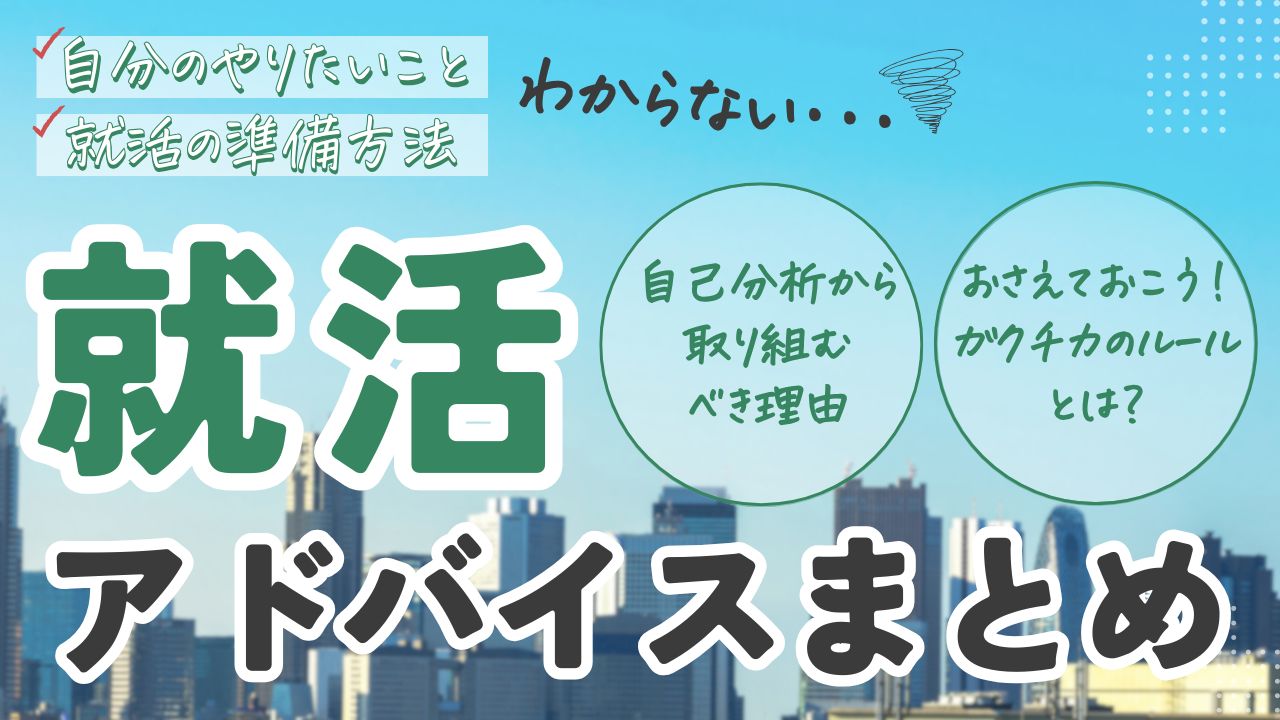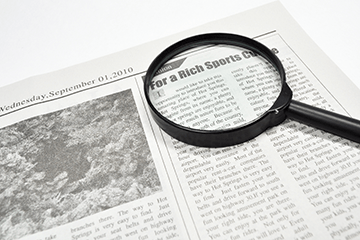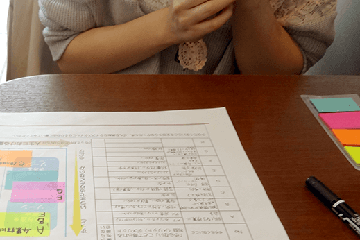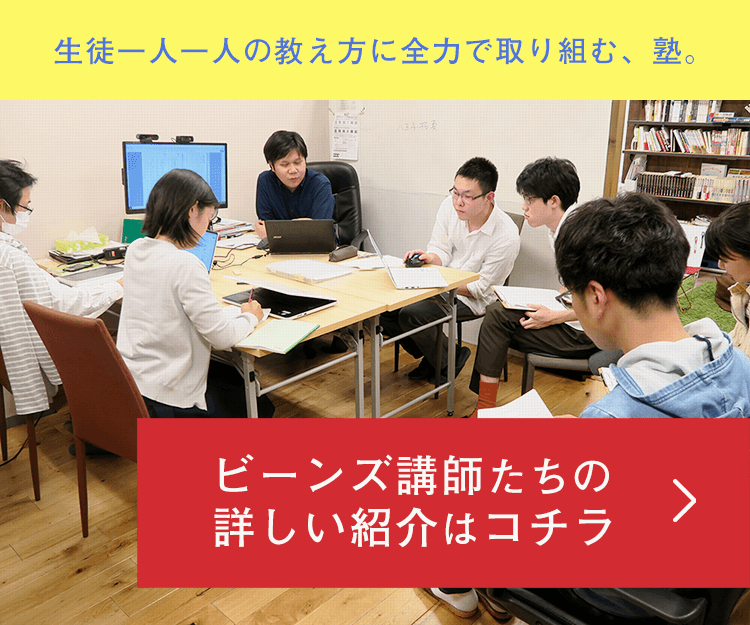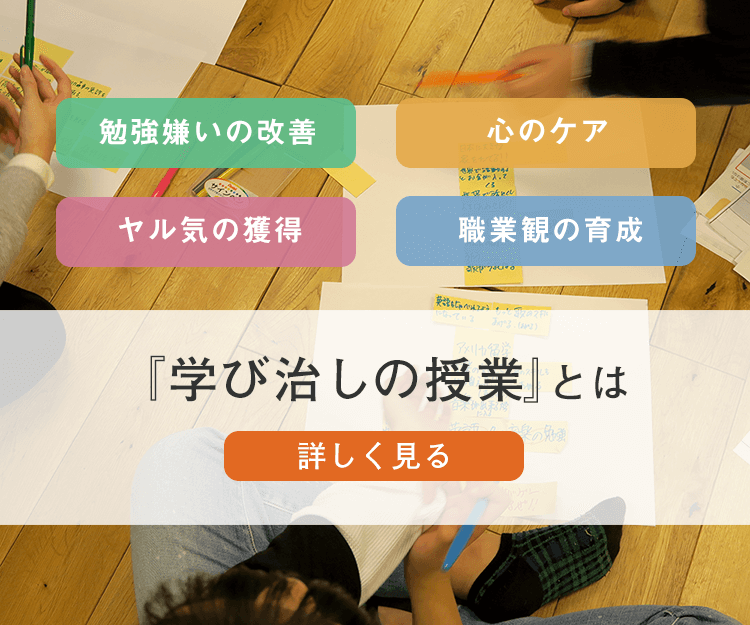大学の不登校で悩む方に知ってほしい「大学生活~今後の就活まで相談できる塾」のこと
不登校になる学生は、小中高だけでなく、大学でも増えています。
また、大学には通っているものの、今一つ大学生活を楽しめないという方もいらっしゃいます。
本記事では、そんな大学生活に関する悩みを持つ方のため、ビーンズよりアドバイスをさせて頂きます。
本記事が状況改善のきっかけになれば幸いです!
(現在、ビーンズでは不登校の大学生へのサポートには受け入れ人数に制限を設けています)
もくじ
大学の不登校で悩む方に知ってほしい「大学生活~今後の就活まで相談できる塾」のこと
大学生で不登校になるケースとは

大学で不登校になる原因には、以下のようなケースがあります。
・単位の選び方がうまくできない
・大学での人間関係がうまくできない
・大学での勉強方法に慣れない(論文が書けない・調べものなど自由性が高い課題がむずかしい)
高校までの間、真面目だったり、内罰的だった学生は、大学における「自主性を求められる勉強・活動」にうまく馴染めず、だんだんと通学意欲をなくしてしまうことがあります。
また、その際、大学に行かず、ネットやゲームなどの趣味に依存すると、そのことで時間を浪費して、さらに不登校が長引いてしまうことにもなります。
状況改善をするための準備(心構え)
これから復学、就活などを考えるにあたって、大事なことの一つが、完璧を求め過ぎないということです。
先ほどの不登校になる原因を振り返った時、それらはいずれも「理想に到達できない自分への責め」という気持ちが根幹にあります。
・きちんと通学しなきゃ、という理想
⇒不登校になって自分を責めている学生の多くは、「大学に行く以上、ちゃんと毎回出席して、授業内容を高校同様、理解しなければならないのに……」という強迫観念を持っていることが多いです。
そして、それができないから、気持ちが落ちていくケースが多いです。(高校時代まではちゃんとできていたのに……などの気持ちも含まれます。)
・人間関係をうまくしなきゃ、という理想
⇒そつなく、できればみんなと仲良くなりたいという願望を持っており、そのギャップで苦しむことが多いです。
とくに、高校までは友達がたくさんいたのに、大学に入って仲の良い友達ができなかったり、周りの人達とノリが違い過ぎたり……こういったことでショックを受けることがあります。
こういった「完璧を求める考え」は(もちろん仕事面などでポジティブに働く面もありますが)大学生活全般においては、ネガティブに働くことが多いです。
それよりも、少し割り切った気持ちを持って、肩の力を抜いて「まぁ、とりあえずこれくらいでいいか」と、考えた方が状況改善はしやすくなります。
▼大学生活では「割り切り」が大事
・授業の内容が完璧にわからなくてもいいや
・単位取得ギリギリでも、単位取得(卒業)できればいいや
・人間関係も仲良くできる子と仲良くできればいいや
このように割り切りの気持ちを持つと、だんだんと「大学へ行きたいのに行けない」といった悩みが減っていきます。
大学には、行ける時に行く。
最低限、単位さえ取れればいい。
こうやって思い切って割り切ってしまうのがおすすめです。
ビーンズでのアドバイス
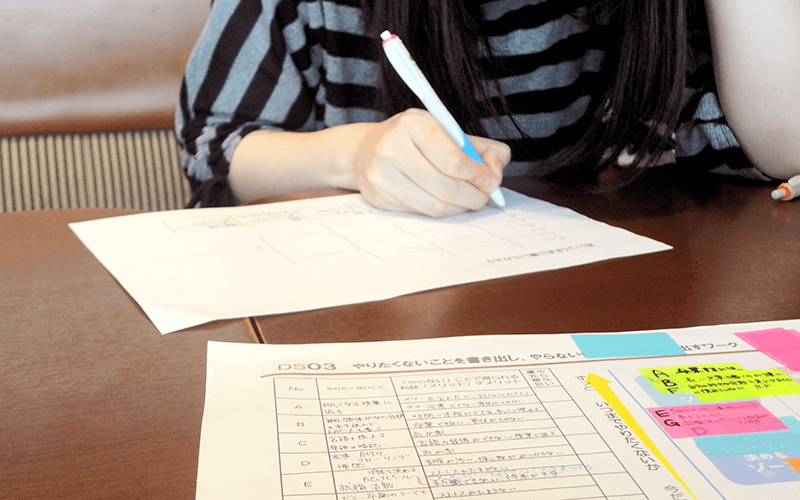
大学への復学支援では、以下のようにアドバイスしています。
・ビーンズのワークで、本人の趣味や方向性をチェック
↓
・本人の興味ある分野に関連する学外活動などに参加してもらう
↓
・色んな情報や人間関係などを得てもらって、そこから動機を得てもらう
(ビーンズからは色んな社会人の方々と話せる機会なども提供しています。)
↓
・「自分のやりたいこと」の方向性が見えてきたところで、今後の進路を決めていく
↓
・単位はじめ、大学のスケジュールを決めて、復学していってもらう
(要望があれば、論文やレポートの書き方指導なども実施)
就活支援においても、上記とほぼ同じ流れです。詳しくは、以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
大事なことは「情報収集」!
おそらく、大学で不登校になっている学生の多くは、自分のやりたいことがまだ見つかっていない状態だと思います。
この時に大事なことは「情報収集」です。
色んな本や映画に触れたり…といった座学もそうですが、
やはり大学時代の学外活動の経験はとても価値があります。
学外活動で、色んな場所に出向いたり、色んな人に会ったり…
学外活動といえばインターンです。
が、インターンがハードルが高いという場合は、サークルでもボランティアでも構いません。
実際に現場へ行って、情報を集めることで、
「これ、おもしろうそうかも…」
「これは自分がやりたいかも…」
という候補を見定めていきます。
学外活動で情報を集め、精神的にタフになる!
なぜ学外活動を薦めるかというと、(大小ありつつ)何かしらの知識や経験を得られることが多いからです。
その中で、自分が大学で学びたい学問や、やりたいことについて考える機会を得られるかもしれません。
また、学外活動で人間関係を構築することによって、コミュニケーションの自信を獲得し、復学した際のゼミ選びなどにも積極的になれます。
学外でも居場所ができることで、いちいち大学の人間関係程度のことに気を取られずに、かえって大学へ行くことにポジティブになれるという効果もあります。。
就活と学外活動
ビーンズでは、大学生の就活支援においても、「とにかく現場へ行ってみよう!」と指導します。
東京の大学生なら、国際フォーラムの展示会や就活イベントはもちろんのこと、受けたい業種があるなら、その関連店舗へ、実際に足を運び、現場の雰囲気、働いている人の雰囲気などを必ず見るようにアドバイスします。
また、できる限り、実際にそこの環境で働いている人と2~3言会話もしてもらうようにもお伝えしています。
百聞は一見に如かず。
あれこれと頭の中だけで悩むのではなく、行動して、実際に会って話してみる。こういうスタンスをとれる人を企業は求めているのです。
参考:センパイの体験談
以前、ビーンズの講師たちにアンケートを取って、大学時代にやりたいことを見つけた経験などを書いて頂きましたので、どうしても自分のやりたいことが見つからない方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、中央大学の学生たちに、これから大学に進む後輩たちへ「大学生活においては色んなことにチャレンジする姿勢が大事」というテーマで特別授業をして頂いたこともあります。
話し手の大学生も決して初めからチャレンジできたわけではない…という点もポイントです。
サポート内容
ビーンズでは、色んな経験をしてきた先生たちに加えて、色んな業界で活躍する社会人の方とも関わりを持っており、生徒の状況に応じて、じかに会って話したり、インタビューしたりする特別授業も実施しています。
過去、復学や就職をした学生の実績(体験談)について、以下に紹介いたしますので、参考にして頂ければ幸いです。
メッセージ
現在、大学生の方へ
大学では、学生ならではの自由性を活かしてほしいと思います。
中学・高校に比べて、大学では、自分に使える時間を自由に設定できます。
大学に限らず、サークル、学外活動、インターン、ボランティアなどに参加したり、または、それらを組み合わせたりして参加して、日々の時間における「費用対充実度」を上げていくようにしましょう。
大事なことは、
・今、自分の好きなものと向き合うこと
・今、自分の好きなものを軸にして、外の環境に飛び込む勇気を持つこと
です。とにかく行動をして、色んな経験を積んでいってもらえればと思います。
保護者さまへ
大学で不登校になり、ひきこもる原因の一つには、ゲーム依存があります。
学校にも行かず、働かず、ずっと遊び続けている。こういう状況がずっと続く時は、自立の心を持ってもらえるよう、甘やかしすぎに注意しましょう。
・子どもの依存がひどい時は
⇒お小遣いカット(趣味のお金は自己負担にさせる)
⇒酷い時は、ネット回線を切るなど、親が制限できる力を持っておく
⇒学校に行かないなら最低限、家の手伝いはさせる
・もし、子どもに暴力を振るわれたら
⇒徹底して、子どもと距離を取る。
⇒お金に余裕があれば、家を離れて暮らす。
⇒一番いけないのはこちらも暴力で対抗してしまうこと。
また、そのまま甘やかしている状態を続けること(親子が共依存になってしまいます)
本来、生活は、生活費や電気代などのお金が必要なことです。
これを、親が上げ膳据え膳やってしまうと、子どもはいつまでたっても自立の機会を得ません。
あまりに依存が酷い時には、子どもに「今の生活維持するためにはどうすればいいのか」と、本人に考えさせるようにしていきましょう。
(大学は義務教育ではありませんし、18歳は、もう社会で働いても良い年齢です。色んな社会の常識を伝えていって、そのことを自覚させることが大事です。)