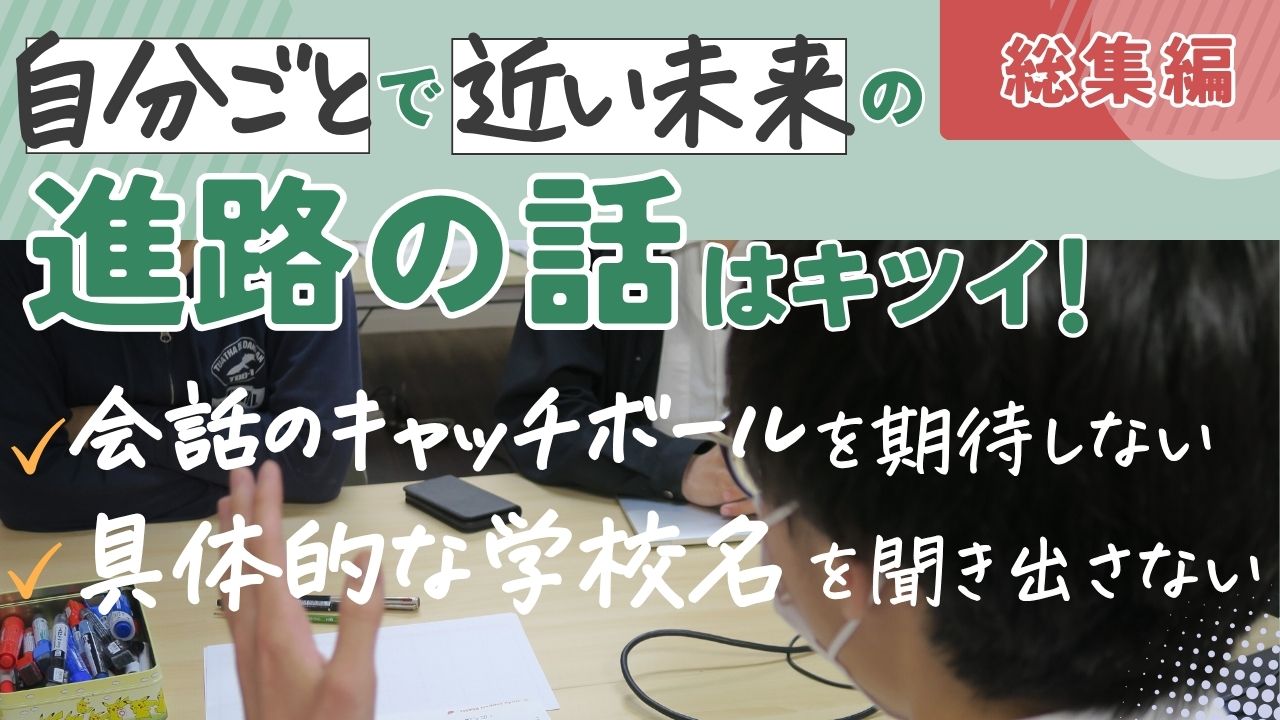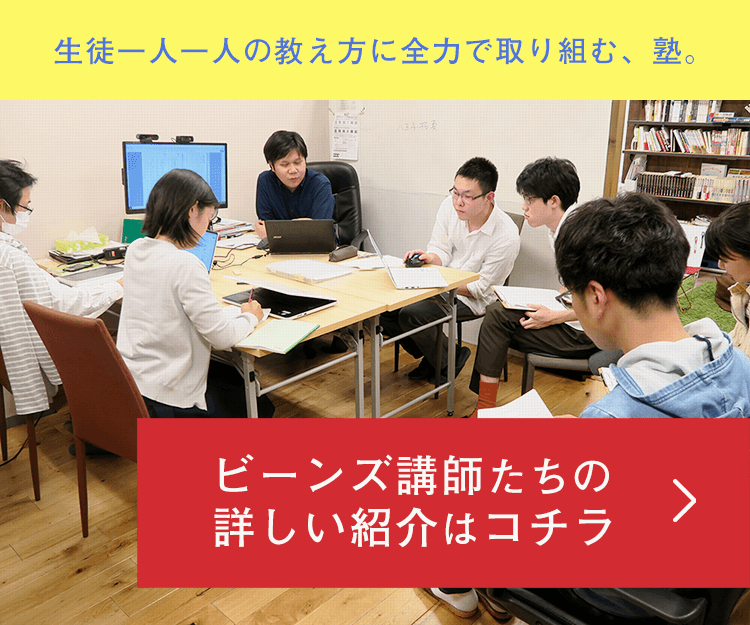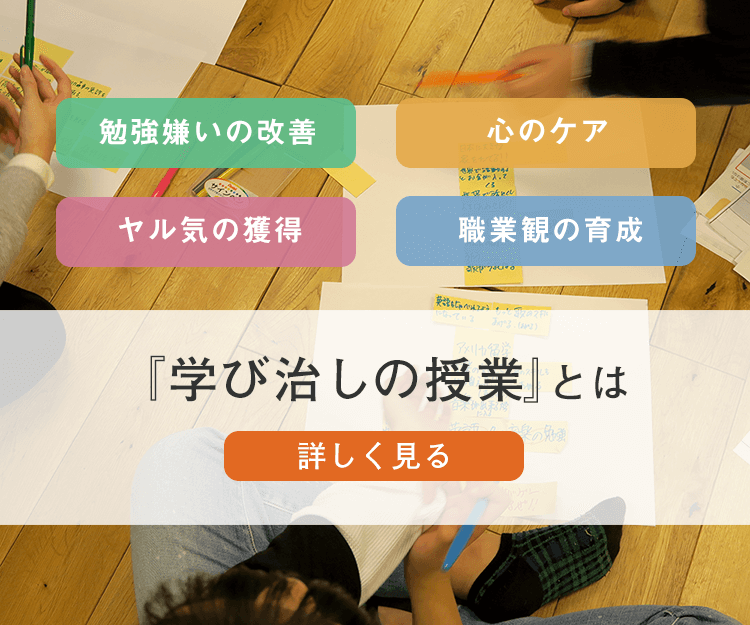中学生・高校生の不登校に疲れた保護者さまに知ってほしいアドバイス

「不登校・勉強嫌いの子どもたちのための塾」ビーンズの塾長・長澤です。
長澤 啓
長澤 啓 NAGASAWA KEI 塾長/副代表 東京大学 経済学部経営学科卒。大学生時代からの現場経験を活かして「悩める10代」のサポート方法を「ビーンズメソッド」として体系化する…
今回の記事では、保護者さまへむけて、特に不登校の最初期に保護者さまに心がけてもらえると効果抜群のコツをお伝えしていきます。
お伝えしたいことを一言でまとめると、「お子さんの状況改善をするために、保護者さま自身の時間を大切にしてほしい」です。
もくじ
子どもの不登校に疲れた保護者さまに知ってほしいアドバイス
お子さまが不登校になった時、最初期にサポートできるのは保護者さましかいません。
だからこそ、お子さまへの不安や心配が増していきますよね。
そのうち、
「私がこんなにがんばっているのに、子どもが全然がんばろうとしない……」
「よその子はみんな学校に行っているのに、どうしてうちの子だけが……」
と、保護者さまが疲れてしまいます。
結果的には、お子さまに対してつい感情的な言葉を投げかけてしまったり、それが原因でお子さまとの関係が悪くなってしまったり……
そんな保護者さまとたくさん会ってきました。
この記事をご覧になっている保護者さまへ、私からお願いしたいのが、
"お子さまのことを考えることをやめる時間をつくる"
"保護者さま自身の気持ちをラクにすることを大切にしましょう"
の2つです。
まず保護者さまに知っていただきたいことは、
・"不登校"という状態自体で、困ることは、かなり限定されます
・"不登校"になって本当に困ることは、お子さまが学校に行かないことではなく、お子さまが自信を失うことです
・"不登校"になってお子さまが自信を失うと、お子さまの状況改善が遅くなります
・また保護者さまもつられて元気がなくなります
お子さまが学校に行かない、不登校になったからといって、そこでお子さまの人生が終わるわけではありません。
ビーンズには、中学校や高校へ行けなくても、自分で進路を選び活躍している・社会に飛び出しつつある子どもたちがたくさんいます。
この記事を読んでいただいているような情報収集に熱心な保護者さまは「不登校=我が子の将来が真っ暗だ」とまではお考えになってはいないはず……
とはいえ、お子さまが学校を休んでしまい、それが長引いてきたとき
「このままだと、我が子の将来はどうなるんだろう……」
「みんなと同じスケジュールで進級や進学ができないかも……」
という心配は、少しずつ大きくなっているのではないでしょうか。
そうしてふとした瞬間に「どうにかしなくちゃ!」と、「恐怖と不安」な気持ちでお子さまと接してしまいます。
※お子さまに進路などの将来について考えて欲しい方は⇓の記事をご覧ください
【中学生・高校生向け】家庭でできる 思春期以降の子どもたちに進路を考えてもらうコツ 総集編
毎年ツクツクボウシが鳴き始めると一気に増えてくるのが 「中学生・高校生の進路決め 高校選び、大学選び」のご相談です…
こうして保護者さまの焦りがお子さまにも伝わると……
もともとネガティブな考えになりがちな不登校の子どもは
「親が自分のことを心配している」
「なぜなら僕は不登校だからだ」
「(やはり)親に心配されるような僕は無価値だ」
とネガティブな思い込みを強め、より状況が悪化してしまうこともあります。
保護者さま自身の気持ちをラクにするためのコツ
ここからは「子どものことで、どうしてもつらい気持ちになることが多い」という保護者さまへむけて、
"保護者さま自身の気持ちをラクにする"ためのコツをお伝えしていきます。
キーワードは
です。
具体的なコツは
☑子どものことを考えることをやめる時間をつくるコツ
子どものために、保護者さま自身の心と健康を大事にする。
たとえば、
「趣味に没頭する時間」
「少し激しい運動」
「熱いお風呂」
「サウナ」
……など、それをやっているときはそのことに集中して、結果、子どものことを考えられなる時間を一日の中にあらかじめ入れこんでおく。
☑保護者さま自身の気持ちをラクにするコツ
子どもに対する期待値、ハードルを下げる
「学校には行けてないけど、健康だしOK」など、我が子のプラス面のみをフォーカスする
さて、上記2つに強く関連することとして「お子さまへの願望」と「自分自身のストレス」との関係ついてお話ししたいと思います。
保護者さまが「自分はこんなに子どもへ尽くしているのだから、子どもはもっと私の頑張りに応えるべき」という気持ちになっていくと、これは同時に保護者さま自身のストレスにもなります。
やがて「自分は子どものためを想ってやっている。なのに、どうして子どもはそれに応えてくれないの」と、
だんだんと子どもを責める気持ちに繋がってしまい、寝ても覚めても子どものことを考えるようになり……
こうなると、お子さまが「どうせ、僕は無価値だ」ループにはまってしまうので要注意です。
(これお子さま相手だけでなくとも、ありとあらゆる人間関係と一緒ですよね)
ですので、ビーンズでは
「特に不登校最初期においては、子ども(相手)の良いところのみ見てあげてください。そのほうが絶対に保護者さまもラクになります。」
「お子さまの事で心配ごとがあったら、お子さま直接ではなくて私たち(ビーンズ)へ愚痴ってください!」
とお伝えしています。
まとめると……
☑「ご家庭で子どもをサポートする際、保護者さま自身の時間を大切にする!子どものことを考えない時間を意図的につくる!」
☑「特に不登校最初期には、子どもに対して期待値を下げる。いいところを探す。悪いところは敢えて見ない!」
ぜひ、これを覚えていただきたいのです。
心配になっている自分自身を客観視してみる
とはいえ、どうしても子どもが心配になるのが"親"というもの。
頭では「親が焦り・不安・心配をすると、子どももネガティブになるというループは理解した。そこから抜け出したい!」と望んでいても、「他の子は学校へ行っていて、うちの子だけが遅れている。こんな"普通のこと"を望んでいるだけなのに、高望みなのでしょうか!」とおっしゃりたくなる気持ち、わかります。
お子さまが生まれてから、今までずっと心配してきたのですから、「いまさら、心配するなって言われもムリ!!」と、おっしゃりたくなる気持ちもわかります。
なので、今日はあえて、ちょっとハードな"特訓"を提案させてください。
自分自身の感情のクセを客観視する
特訓とは「ご自身の感情のクセを客観視する」というものです。
親というものは、どうしても子どもへ「将来のための成長」を求めやすい性質にあります。
「お子さまが生まれた→首が座ってほしい→次は立ってほしい→はやく歩いてほしい→しゃべってほしい→ひらがなを覚えてほしい……」など、保護者さまは次から次へと"子どもが成長することへの欲求"が生まれます。
そして、その中で必ず「他の子と比べて」います。
最初は、「うちの子は喋るのが早くて、立つのが早くて……」ぐらいが、やがて「うちの子はほかの子よりも勉強ができて、運動ができて……」となっていきます。
客観視をして欲しいのは「親として自分が子どもへ成長してほしいという欲求をもっていること」「我が子をよその子と比較した際に、焦りや不安が出る」など、「自分の感情のクセ」なのです。
自分の欲求や感情を記録して冷静に振り返ってみる
「自分の感情のクセ」がわかってきたら、今度は、"子どもが成長することへの欲求"が強まった時のことを日記などにメモしてみてください。
あ、お子さまへのイライラもついでに書いてもいいですよ!(ビーンズの保護者さまには「お子さまへのイライラは一旦記録して、僕らへあとで教えて!」とお伝えしています)
たとえば、「他の子が楽々とできる工作があんまり上手じゃなかった。とても焦る」というような気持ちの揺れ動きがあり、2日くらい不安になったことがあったとします。
このことを後になって振り返ってみると、そういった不安というのは保護者さまにとってはストレスになるだけですし、心配したからといってそれでお子さまの工作が上手くなるわけでもない、と気づけます。
こういったことを繰り返すと「自分は、(後から見ると)どうでもよいこと・些細なこともたくさん心配してしまっているなあ」と気づく(かも)しれません。
特に以下のような心配をいつもしてる……ということに気づけたらラッキーです!
気づけたらラッキー"感情のクセ"2大パターン
⇒あの時あの学校を受けさせなければよかった……
⇒もっと勉強させていればこんなことにはならなかった…… など
⇒このままでは、我が子はどこにも就職もできない……
⇒40になっても親にパラサイトするのでは…… など
できることなら「2大パターンに当てはまる心配は、きっぱりしない・考えないと決める!」としていただくほうが、保護者さまにとっても、お子さまにとっても良いのです。
しかし、私たちプロの講師でも、担当している子どもとの関係性が深まると、ごくまれに心配が強くなっていきます。
その心配がかえって子どもに悪影響が出てしまう場合があることが分かっていてもです。
ビーンズで講師をやるということは、毎日がその葛藤との戦いです。
まして保護者さまは私たち講師の何倍もお子さまを愛してらっしゃいます。
私たち講師には絶対にかないません。
"子どもを愛しているからこそ、強く心配してしまう。"
ということは実に自然なのです。
自分の「感情のクセ」を知っておくと少しだけ余裕が生まれる
ただ、ここまでこの記事を読んでくれた保護者さまは「親の心配がかえって子どもにマイナスになる場合もある」ということは、ご納得いただけていると思います。
「昨日まで学校に行くって言ってた子どもが、朝になっても学校に行かない……」そんな時を想像してみてください。
「どうしよう……」「なんとかしないと……!」「このままじゃ将来が……」という不安な気持ちになりますよね。
この時、自分の"感情のクセ"を把握している人であれば、「今、自分(保護者)は子どもが不登校で焦っている、色んな不安がある。でも、そのうちのいくつかの不安は、(いつもみたいに)今考えても仕方ないことなのかもしれないな」と、感じることができます。
実は、私たちビーンズの講師が子どもへの心配が強くなっているな……と自覚したときにやっていることがコレなのです。
そうすると、ちょっとだけですが、こちらに心の余裕が生まれます。
大人側に余裕が生まれれば、自然と子どもへかける言葉が変わります。
例えば、心に余裕がないと、「今日、学校行くって言ってたよね?」と言ってしまい、お子さまとケンカになってしまいます。
しかし、余裕が生まれると、「今日は仕事早く上がるから、久しぶりにすき焼きを食べよう! でも、お母さん全然買い物してなくて、悪いんだけど夕方スーパーへ来てくれない?」といった言葉がけに変わります。
すると、お子さまの反応が変わります。
そのちょっとの心の余裕が生んだ言葉は学校へ行けず苦しんでいるお子さまの心をちょっと軽くし、状況改善の糸口につながっていくのです。
※お子さまとの会話のコツについて詳しく知りたい方は⇓の記事も併せてご覧ください。
中学生・高校生のお子さんが不登校・引きこもりになったら……【まずは親子の会話量を増やそう】
本記事では、不登校・引きこもりの中学生・高校生のお子さんにとって「ご家庭を絶対安心の場」にする意義と、「ご家庭を絶対安心の場」にするための方法について説明します…
とにかく不安な保護者さまへ。ぜひ相談を
ここまでお話してきましたが、保護者さまご自身の不安が日々増していって「とてもじゃないが自分を客観視なんてできる状態ではない」という方もいらっしゃると思います。
特にお子さまを愛してらっしゃる保護者さまほど、その傾向にあります。
もしそのような状態でしたら、ビーンズにご相談ください。
ビーンズの子どもたち・ご家庭の豊富な事例から、
など、ご家庭でできる状況改善に向けたアドバイスをさせていただきます。
お子さまを深く愛してらっしゃる保護者さまだけで、お子さまへの客観的な見方を獲得していくのは大変です。
多くの子どもたち・保護者さまたちと日々接している、僕らのような存在にぜひ頼ってほしいと思います。
ビーンズの授業や子どもへの接し方の基本的な方針をお知りになりたい方は以下の記事をご覧ください。
ご家庭でのお子さまへの接し方へのヒントがあるかもしれません。
学習支援塾ビーンズ 『学び治しの授業』の流れを詳しく解説します!
学習支援塾ビーンズ 『学び治しの授業』の流れを詳しく解説します! 本記事では、 ・ビーンズがお子さまと保護者さまに提供している授業やサポート ・保護者さまからよくいただくご質問 ・ビーンズに通い、元気になったお子さまの例…
また、「ビーンズの他の保護者はどんな感じだったの…?」ということについては
集英社 『LEE 2024年10月号』"「行き渋り」「不登校」その後の選択" にビーンズ保護者様の声が掲載されています。
こちらもぜひご覧ください。