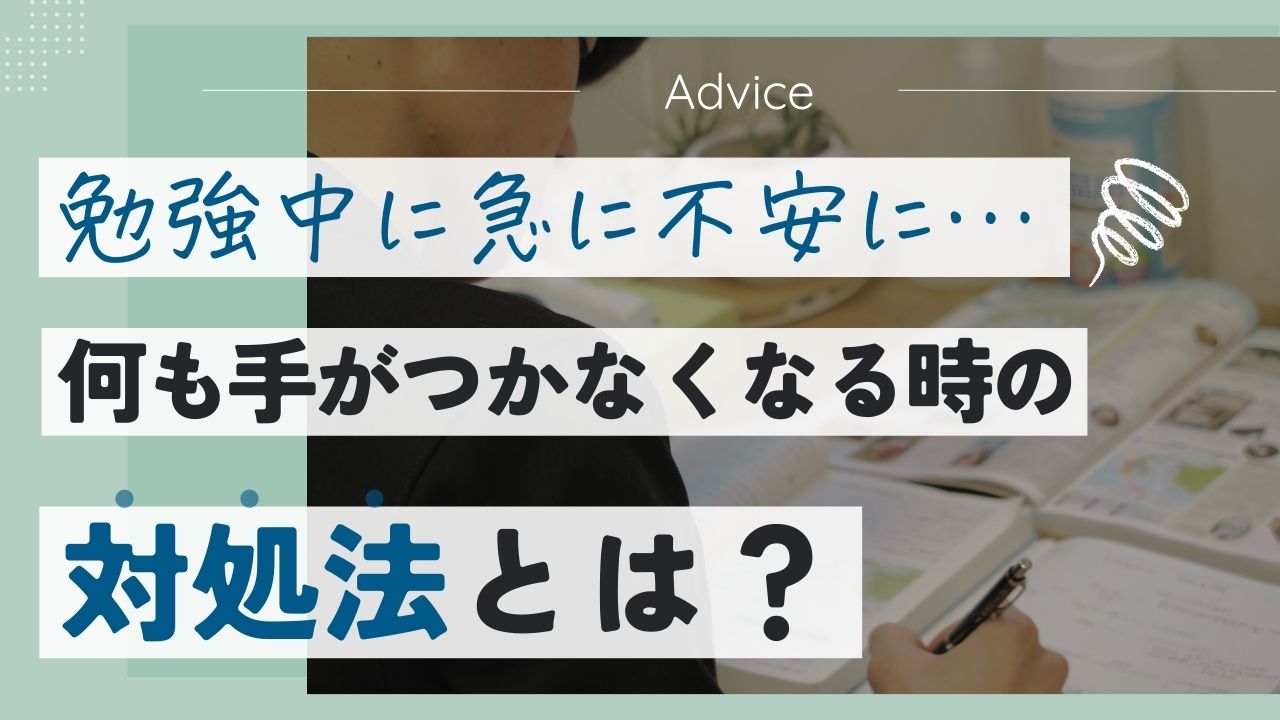清水 基頌

清水 基頌
SHIMIZU MOTONOBU
SV/2代目 副教室長
愛称は「のぶのぶ先生」。中学校3年間の不登校経験を経て、通信制高校に進学。通信制高校時代に陸上競技で全国大会5位入賞を果たす。
競技を通じて得た自信を糧に、大学受験に合格。大学では教育学や心理学を学ぶ。
ビーンズでは、多くの個別/集団授業・受験伴走を経験。現在は豊富な授業経験と保護者対応の経験を活かし、SVや副教室長など、各方面で活躍中。
趣味はビーンズ、お散歩、日光浴。
ビーンズでやっていること
授業
雑談授業から、大学受験(総合型選抜)・高校受験(チャレンジスクール)対策の授業まで、幅広く担当しています。
授業では、生徒との何気ない会話や自己分析を通して、それぞれの「軸」を一緒に見つけていく時間を大切にしています。
生徒が自らの意志で「自分の生き方」を選び取っていく姿に、何度も心を動かされてきました。
将来に不安を感じ、迷いを抱えながらも一歩ずつ前に進もうとする生徒の姿に、いつも尊敬の気持ちを抱いています。
生徒たちに少しでも寄り添えるように、心を込めて授業を担当しています!
SV(スーパーバイザー)
SVとは、担任講師をサポートする役割です。
ビーンズの担任は、生徒指導の中期方針を考案し、保護者と面談する、ビーンズのエース講師たちです。
その担任と定期的に面談を実施し、丁寧に生徒の状況や中期方針決めで悩んでいるところがないかをヒアリングしています。
担任が迷いなく生徒の指導方針を立てられ、そして講師がストレスなく授業を実施出来ること。
これが、生徒の「4つの時期」の移り変わりを後押しするために必要なので、とにかく丁寧さを意識しています!
副教室長

毎日の授業やイベントが滞りなく実施出来るよう、BFS運営のマネジメントも含めた教室全体のスケジュール管理を行っています。
その他にも、教室長の補佐として以下も行っています。
副教室長の仕事
- 講師の適切な配置
- 月の授業のコマ数の管理
- (自分を含む)SVたちをサポート
- 講師全体へのサポート方針の考案
- 授業料の請求業務(経理外注メンバーへ連絡&請求システムに登録)
憧れの先輩も就任していたポジションなので、精一杯頑張ります!
TUメンター
ビーンズのパーパスである
「なんだかんだで毎日楽しく生きていける人があふれる社会をつくる」
をともに達成する仲間を増やすために、社会人講師(「TU講師」と呼んでいます)の育成に力を注いでいます。
社会人の方からいただく質問は、どれも鋭くて深いです。
質問をいただくことは、私がビーンズメソッドをより深く学ぶきっかけをいただいていると認識しています。
TU講師事業を通して、世代を超えてビーンズの仲間が増えてくれることがとっても嬉しいです!

生死をさまよう大事故から
「再始動」
中学3年間不登校だった私がビーンズ副教室長になるまで
「将来、不登校のこどもたちに寄り添える体育教師になりたい!」
そんな夢を胸に大学に進学した私は、学習支援塾ビーンズでボランティアからキャリアをスタートさせました。
自身の不登校経験、インターンとしての圧倒的な成長、そして生死に関わる大事故を経て……
私は今、ビーンズの副教室長として、再びこのフィールドに立っています。
これは、私の逆境⇒努力⇒成功のストーリーであり、自分自身を深く見つめ、行動していった軌跡です。
中学不登校

「一問のミス」で、自分の存在が否定されるように感じた中学時代
小学校時代は、教室で元気に発言をするタイプでした。
しかし、中学校に内部進学した際、環境の変化と自分の中の完璧主義が原因で、状況が一変します。
私にとって「一問のミス」は、自分の存在そのものへの否定に繋がる…ように感じてしまう大きな出来事でした。
努力しても不安が募り、努力しないともっと不安が募る…という悪循環に陥ってしまいました。
そして、中学1年生から3年生まで不登校になりました。
これは、ビーンズの生徒にも多く見られる、「完璧主義」そして、
「過度な一般化をともなう自己否定」 の苦しみそのものだったと思います。
部活を通して学んだ宝物
「このままではいけない」という強い焦りと、不登校という現実から逃げるように、私は部活動である陸上競技に打ち込みました。
当初はスタメンにも入れないほどの走力。
練習でも、小さな敗北と失敗を重ね自己嫌悪に陥りそうになる自分を何とか励まし、毎日練習を重ねました。
すると少しずつ結果が出てきます。
まず、スタメン入り。
そして大会に出場しても結果がついてくるようになりました。
市大会では6度の優勝。
そして県大会で5度の入賞(最高順位3位)…という実績を手にすることができました。
陸上競技を通して、私は
「自分の課題を見つめる」
「自己管理をする」
「自律する」
という、今の活動に通ずるスタンスを学ぶことができました。
また、部活動で仲間との関わりを通して
「他者を承認する」
「他者から承認される」
という経験を通し、居場所と仲間を得られたことも人生の財産となりました。
進路選び 自分の逆境を"原体験"に
その後、通信制高校に進学しました。
新たな環境で、勉強と自分の進路について真摯に向き合いました。
将来を考える中で、自分の(本当に苦しかった)不登校の経験が活きてきます。
不登校経験が私の中での"原体験"となり、進路を選択するエネルギーを生み出していったのです。
そして自己分析の結果「思春期の子どもたちの道しるべとなる保健体育教師」を志し、そのために大学受験をすることを決意しました。
さらに自分の不登校を含めたさまざまな経験や、そこからのいきさつを活かすために、一般受験ではなく「総合型選抜」で大学受験に挑戦しようと決めました。
もちろん当時の私の周りには(そしてビーンズの生徒にも)
「まだ社会に出るのは怖い…」
「大学に入らないと将来が不安」
そういった理由で大学を選ぶ人もいます。(し、そういう気持ちは僕も痛い程わかります!)
が、私の場合は自分の原体験に深く紐づいた、大学での学び、意味のある将来へ向けた総合型選抜…です。
俄然やる気が出ます。
もちろん、
「大学の総合型選抜にために/将来教師になるために/ビーンズのメンバーになるために中学三年間の不登校になったわけではない」
「不登校当時の自分は(そもそも)そんな将来のことは考えていない」
これが事実です。
自己分析を行っても(当たり前ですが)「不登校」という過去におきた事象自体は変化しません。
しかし「過去は未来によって変えられる」のです。
これはどういうことかというと…
総合型選抜を含む大学の推薦入試対策やチャレンジスクール対策で自己分析をおこなうことで、過去の辛かった経験が、自分の将来への軸、将来へ向かう原動力となることです。
私の場合、自分の中学校時代の不登校の経験が大学総合型選抜対策の自己分析の中で
「なぜ不登校支援をしたいのか?」
「なぜ教師になりたいのか?」
「なぜ体育教師なのか?」
を貫く軸となり、キラーストーリーづくりの中心になりました。
そうして「しんどかった不登校時代」の経験を「進路を決める原体験」として意味付けし直し、
(完全ではないにしろ)
「不登校の経験は、今の自分をかたちづくる時間だった」
…と過去を(ある側面において)ポジティブに読み替えることができるようになっていったのです。
これら一連のことを、ビーンズでは「過去の再編集」と呼んでいます。
過去の不登校経験を原動力に変えて、進路の方向性も決まり……
さらに
陸上での全国大会5位入賞
英検合格といったガクチカをつくり…
第一志望の大学に総合型選抜で合格することができました。
夢の実現に向けて…
焦りから飛び込んだボランティア
大学1年生の夏休み明け…
「将来、不登校のこどもたちに寄り添える教師になりたい」という夢に向かって進めていない現状に焦りを感じていました。
そんな時、不登校の子どもたちに寄り添うビーンズの活動を知り、ボランティアに参加を決意します。
課題だったのがビーンズまでの距離です。
自宅から片道2時間かけて参加していました。
そして、活動が楽しすぎて終電を逃す(笑)なんてことも。
その後、ビーンズのインターンプログラムに参加し、段階的にスキルとスタンスを磨いていきました。
ベーシックコースで基礎を固める
生徒の「4階構造」うち、「青春経験」(3階部分)を組み上げていく、生徒の「居場所」…BFS(ビーンズフリースペース)で活動しながら、先輩インターン生から研修を受けていました。
アドバンスコースでチーム活動
このコースでは、より実践的で発展的なスキルや、チーム経験を積むことに注力しました。
頑張ったことの一つとして、私はBFSにて「夏祭り」や「室内スポーツイベント」を企画しました。
また仲間と共に、ビーンズ内の制度であるSVの設計や、
担任講師の増加pjtを達成するなど、「熱い青春」をチームで経験することができました。
これらの経験を通して、チームビルディング やリーダーシップ・フォロワーシップを学び、
後に必要となる組織運営の基礎を身につける貴重な経験でした。
プロフェッショナルコース
ベテランインターン(講師)として、生徒対応のProとして、また生徒の担任として、
あらゆる生徒でも対応できるようになることを目指すコースです。
ここでは、チャレンジスクール対策でエンカレ授業やグループ授業を実施しました。
特に、都立高校チャレンジスクール対策では、受験生である生徒たちが自身の不登校経験と真正面から向き合い自己分析をする必要があり、講師として生徒の「変化のストーリー」を共に言語化する難しさとやりがいを感じました。
また、このころ6名の生徒の担任を務めており、保護者さまのお悩みにも寄り添えるようになってきました。
そしてチャレンジスクール対策で得た経験をもとに大学受験生のグループ授業を担当し、自己分析〜志望校選びを伴走することで、生徒の進路実現をサポートする専門性を高めました。
この期間を通じて、私はビーンズが目指す「地に足ついた進路伴走」に必要なスキルを体得しながら実践しました。そうして生徒一人ひとりの変化を間近で見ることができたのです。
事故 そしてパーパスとの再会
究極の"ままならなさ"と自己対話
順風満帆に活動していた2025年6月、私は交通事故に遭いました。
鎖骨骨折をはじめ、満身創痍に。
「当たり所がもう少し違っていたら…」
「もう少しだけ大きな自動車だったら…」
「落下したところがもう少し硬い地盤だったら…」
私はここにいなかったかもしれません。
一命をとりとめたものの、自由にならない身体、夜も横になって寝れない日々…
本当はもっと活躍したいのに、本当はもっといろいろ経験したいのに、大学にもビーンズにも行けない、というより日常生活すらまともに送れない日々が続きます。
自分の力ではどうしようもない。まさに究極の「ままならなさ」。
そんな状態の中でも、頭から離れなかったのはビーンズの生徒たちのことでした。
動けない身体で、私はひたすら自己と対話し、自分の本当にやりたいことはなにかを考え続けました。
極限の逆境に置かれた時、私の中で確固たるものとして残ったのは、ビーンズの存在意義でした。
そこで私は、「ビーンズのパーパス達成に貢献し、日本中の不登校のこどもたちと、その保護者のサポートをする」ことを決意します。
この事故による活動停止は、私自身の「過去の再編集」を行う機会にもなりました。
不登校だった過去も。
陸上での成功も。
インターンでの学びも。
そしてこの大事故さえも…
これら逆境の経験すべてが、ビーンズのパーパス実現のために活かせる…と確信したのです。
そして「なんだかんだで毎日楽しく生きていける人があふれる社会をつくる」へ繋がっていると、腑に落ちたのです。
ビーンズ副教室長として再ジョイン

そして私は、ビーンズに副教室長として復帰しました。
私の個人的な経験…
不登校からの部活に打ち込んだこと。
高校進学から進路を考え、大学受験をめざしたこと。
事故からの生還、そして再起…
私が経験したこれらのことは、今、私が悩める10代とその保護者さまの「ままならなさ」をなんとか理解し、寄り添うための道しるべ、
そして共に次のステップへと進むための「ゆるやかスロープ」 を描くための地図になっている…そう信じられています。
動画紹介